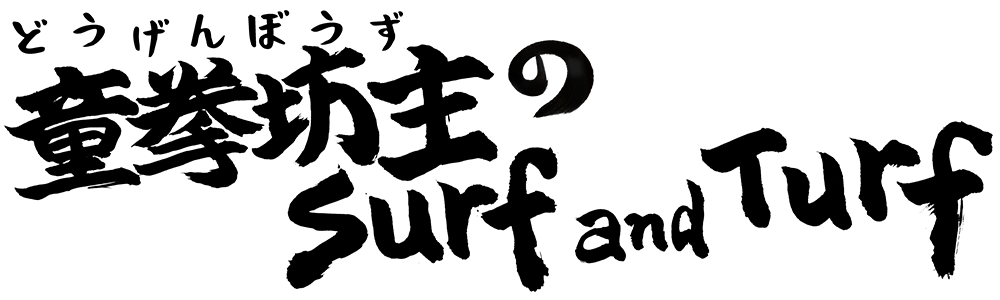「中間支援組織」が空き家問題解決のカギになる!

INDEX
ここ数回の記事で、豊北町の空き家問題を取り扱っています。
ふりかえり:豊北町の空き家問題
小さな空き家 = 住宅の空き家
まず、常に人が生活のために利用している(=住んでいる)状態ではない住宅、って意味のいわゆる「空き家」。
大きな空き家 = 遊休公共施設
それから、閉校した学校の校舎や、100戸以上空いているという市営住宅などの遊休公共施設。
これらの空き家問題を、まちづくり協議会などの市民団体だけで解決しようとしても、ボランティアでは限界があるし、ビジネスにしようとすると法的な問題が生じる場合があります。
それなら行政にお願いしたいところですが、財政の厳しい中、限られた予算で空き家対策の優先順位は高くありません。
今ある 空き家バンク制度 をなんとか活用したり、個人やアマチュアでできる限りの対策をしていくことしかできないのでしょうか…
中間支援組織とは
今年度、豊北町にパソナグループの 瀬川康弘 さんが地域活性化起業人として着任され、豊北町のまちづくりに新しい風が吹いています。
また、今年度は パソナJOB HUB が萩市と豊北町でテレワークを推進する事業を進めており、これにはわたしも主に「まちのキーパーソンとパソナJOB HUBさんをつなぐハブ」的なポジションで関わらせていただいています。
そんな中、わたしは何度かパソナJOB HUBの皆さまとミーティングをする機会を得たのですが、そこでハッとしたアイデアがあります。
それは 中間支援組織 という存在です。
豊北町の空き家問題でシミュレーション
ちょっとここで、豊北町の空き家問題を解決するプロセスをシミュレーションして、中間支援組織が活躍する場面をイメージしてみましょう。
空き家の確認
空き家問題解決の第一のステップは、空き家の確認です。あの家、人が住んでるの?住んでないの?の確認ですね。
「どの家がどんな状態の空き家なのか」っていう 空き家調査 を行うときは、外部の業者に委託するよりも、自治会長などの地域住民が行った方が、空き家の持ち主さんの信頼も得られやすく、スムースに進めることができます。
スーツ着た人が田舎道を歩いてきて、
「お隣りの家って人が住んでおられないようですが、空き家ですか?」
「よろしければ持ち主の方の連絡先を教えていただけないでしょうか?」
なーんて訊かれても、特にこのご時世、迂闊に答えてトラブルに巻き込まれてはいけない!って思っちゃいますよね。
それよりも自治会長や知っている地元の人が来て
「(隣りの)〇〇ちゃん、たまに車は停まっちょるの見るけぇ、風は通しに帰ってきよるみたいじゃけど、家はどうしたいって言いよるほかね?」
ってほうが、
「それいね。仏壇があるけぇ仕方ないとは言いよるけど、はぁ福岡に家建てちょるし、子どもも皆福岡じゃけぇ、なんとかならんかのーって言いよったんよ。空き家バンクみたいなのありゃ教えちゃってーね」
みたいな、ご近所さんもむしろ積極的にお世話してあげたい気持ちになるかもしれません。
空き家の利活用
さぁ、シミュレーションでは、地域の方のご尽力、ご近所さんのご協力で、活用できそうな空き家が見つかりました。一歩前進です。
空き家の確認は、外部の業者より、地域の方が動いてくださったほうが良さそうというイメージもできましたね。
一方でそこから話が進み、実際に 空き家のリノベーション であったり、入居希望者の審査 であったり、入居後の維持管理や保証について考える段階になったら、専門的な資格を持った業者さんにお願いした方がリスク回避になります。そもそも素人でそんな不動産の仲介業のようなことをやっていいのかどうかも定かでありません。
先の記事でも書いたとおり、ほうほく未来応援隊 の会議で空き家問題について話し合った際も、
空き家の維持管理等については、行政から委託を受けた業者が行ってくれることが望ましい
と言う意見が出ました。
例えば まちづくり協議会の担当者(普通のおじさん) が、入居希望者の面接を行ったり経済状況などを確認して
「よっしゃ、アンタ入居していいよ」
って判断したとします。
ところが、いざ入居させてみたらその入居者が、ゴミの出し方は守らない、スピーカーのボリュームの下げ方を知らない、家賃は滞納する…と大問題人物だった!
みたいなことがあった場合、「誰がアイツの入居を許可したんじゃ…!」って話になっちゃいますよね。
普通のおじさんにそこまでの責任は求めちゃいけません。
それから、例えば入居した直後に家の柱がボキーン!!折れました、とか、電源のブレーカーの容量がこんなに小さいとは聞いていませんでした、とか、入居前のメンテナンスや入居時に本来必要な確認事項が漏れてた、みたいなケースも発生しうる。
ですから入居の契約に関わる審査や人物の保証などについては、プロの目線でしっかりやっていただくのが良い。
だから、まち協の会議では、行政で不動産業者さんに業務委託してもらえんですかね…って話になったという流れです。
しかし繰り返しになりますが、実際の財政状況を考えると、インフラ整備等、住民の生活に直結する問題解決のための予算ですら確保が厳しい状況の中、移住者促進のために避ける予算は限られているというのが現状のようです。
不動産屋さんにしても、田舎のポツンと一軒家を自社で管理する物件として抱えて、入居者があるまで維持していく、というのはなかなかのハイリスク。儲かる案件ではありません。
そんな時に、地域に住む不動産会社に勤める、宅建の資格を持った住民が
「その空き家の管理、オレできないかなぁ」
とつぶやいたとします。そして、それを聞いた地域の大工さんが、不動産屋さんの思いに賛同し、
「じゃあその空き家のリノべーションは、ウチの工務店で請け負うよ」
と名乗りを上げ、それから次々に、行政との調整を行う人、次の空き家を見つけてくる人、広報をしたりポップを作ったりする人…。
「七人の侍」や「ワンピース」のように、次々と仲間が集まり、地域の課題を解決するチームができる。これが、中間支援組織のイメージです。
それも、このシミュレーションではそれぞれの能力や特性を生かすことができるプロ集団ができていってます。そうなると色々な活動が手っ取り早く実現しそうです。
中間支援組織の形態は、その活動に必要な経費を政府や自治体の補助金から賄うのであれば、任意団体でも構わないと思いますが、活動を通して利益を上げ、それを活動資金としたり事業を拡大したりするのであれば、法人の形を取った方が良いかもしれません。
このたびミーティングに出席されてた パソナJOB HUB の方の地元 広島県三原市 では、株式会社まちづくり三原 と言う中間支援組織が、様々な地域課題を解決する活動を行って活躍しています。リンクを参照すると、中間支援組織の活動のイメージがよりしやすいと思います。
わたしの目下のテーマである
「まちづくりを学問、仕事に!」
に込められた意味の大きなヒントが中間支援組織にあると感じます。
まちづくりを学問・仕事にしていくために
かつての日本の教育では、何故かお金を稼ぐことについてほとんど教えてくれないばかりか、むしろお金をガツガツ稼ぐこと=悪とも取れるような教育をしてきました。
現在では、小・中学校からアントレプレナーシップにつながる内容が含まれてきているようですが、なにしろそれを教える先生が、そういう教育を受けていないし、ビジネスの経験もないので、これでイケる!というスタイルの確立にはまだ時間がかかりそうです。
さらに、とかく田舎では、サービスに対する対価の概念がバグっていて、コミュニティーのために自己犠牲を払うことが当たり前のようなカルチャーが根強いように感じます。
まちづくりはボランティアでするもの
「まちづくりで金を稼ごう」なんて考えてはいけない
そういう雰囲気が今の時代、最初はやる気に燃えていた住民をいずれ疲弊させ、新規参入者の障壁となり、まちづくりがうまく回ってこなかった原因になっているのではないでしょうか。
近年「シェアリングエコノミー」や「限界費用ゼロ社会」などが注目され、世の中は「消費のための生産」から脱却しようとしています。これって最先端の考え方で、一見
「なにそれ?ウチみたいな田舎にゃ関係なくない⁉︎」
ってスルーしちゃいそうになるかもしれませんが、わたしは、実は田舎にこそハマりやすい考え方だと思うんです。空き家の利活用なんかまさにそれだし、マルシェだったり、おすそ分けのカルチャーだったり、シェアリングエコノミーで説明できる文化や地域課題がたくさんあります。
今ある資源を活用しながら、リノベーションまちづくりをうまく回転させ、しかも生活に必要な収入がしっかり得られる、そんな まちづくり が期待されている時代、豊北町には材料が全て揃っているのではないかという気さえします。
市民団体と行政をうまくつなぎ、新たなビジネスを生み出していく、そんな中間支援組織が活躍するまちづくりを考えていきたいなと思います。