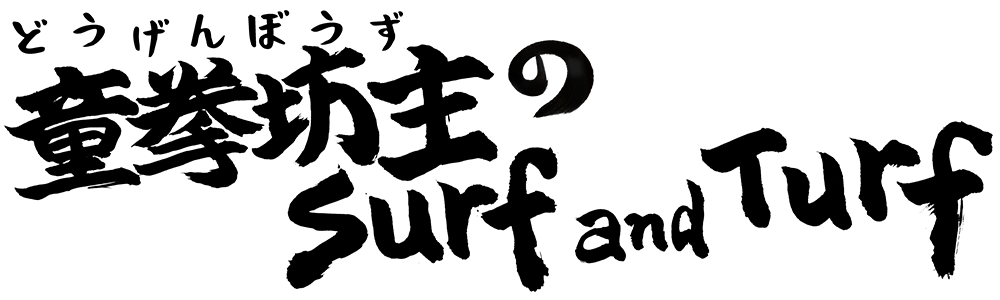意外と知らない「赤い羽根共同募金」。あなたのまちづくりに、もっと活用できるかも
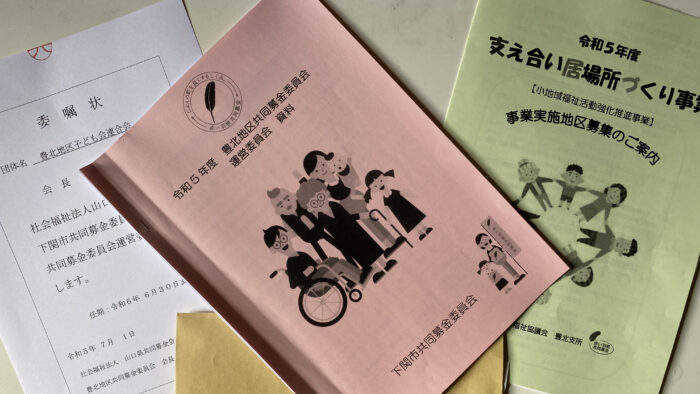
INDEX
2023年度は子ども会の会長になったことで、町内の様々な活動や団体の役員や委員のリストに組み込まれる羽目になり、いくつもの会議に出席しています。
そんな委員のひとつが「社会福祉法人山口県共同募金会下関市共同募金委員会豊北地区共同募金委員会運営委員」です。メチャメチャ長い役職名ですが、要は豊北町の 赤い羽根共同募金 の運営委員です。
赤い羽根共同募金って、小学生の頃から、年末に募金してそれこそ赤い羽根をもらって制服の胸につけたりしてたな…って記憶はありますが、実際そのくらいのことしか知りませんでした。
皆さんも、「共同募金とは?」って言われても、明確に「これです」っていうの、意外と知らなかったりしませんか?
赤い羽根共同募金とは
共同募金のWebサイトによると
共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりました。
当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。
社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれています。
赤い羽根共同募金 Webサイトより
…ってことで、戦後の福祉施設の支援から始まり、現在は地域福祉の課題解決など、福祉に関わる目的に活用されている制度なんですね。
だからその事務を各地域の 社会福祉協議会 が担っているというわけです。
今回わたしは、豊北地区の運営委員会に出席してきましたので、その内容をシェアするとともに、気づいたことや活用のアイデアなどについても紹介します。
豊北地区の共同募金の現状
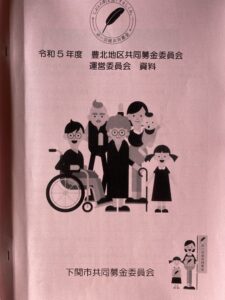
赤い羽根共同募金の種類
まずこれも初めて知ったんですが、赤い羽根共同募金って、大きく分けて2つの種類があるんです。知ってました?
ひとつ目は「一般募金」です。これは毎年度、10月から翌年3月までの6ヶ月間の期間で行われているもので、翌年度の地域福祉活動のために使用されます。
スーパーやコンビニのレジ横や、官公庁などに箱が置いてあるのを見たことがあると思います。
きっと年中置いてあったとしても、地域の社協に届けるのは10月から3月の間なんでしょうね。
で、もうひとつが「歳末たすけあい募金」です。これが冒頭わたしが思い出した、年末に募金してたアレなんですね。
これはなんと、その名称どおり、年末に行われる福祉活動 に使用されます。「年始応援セット」を届けたり、一人暮らしのお年寄りを訪問したりという、年末年始ならではの、まさに「たすけあい」の福祉に活用されている、っていうのは、知るとなんだか協力したくなりますね。
豊北町の状況(募金実績)
さぁ、では豊北町での2022年度の赤い羽根共同募金の状況ですが、
一般募金 1,978,058円
このうち、791,223円 が県内の福祉活動に、
1,186,835円 が2023年度の豊北町内の福祉活動に使用されます。
ちなみに、前者の「県内の福祉活動に使用する」分を「県域配分(A配分)」、後者の「豊北町内の福祉活動に使用する」分を「地域配分(B配分)」と呼ぶのだそうです。
歳末たすけあい募金 1,135,670円
このうち、700,000円 が町内7地区の社協へ10万円ずつ配分され、歳末見守りネットワーク事業などに活用されたということです。
歳末たすけあい募金の残額 435,670円は、次年度、つまり今年度のB配分に追加されることになっています。
今年度のB配分にはさらに2022年度のB配分余剰金の 107,000円 が追加で計上されます。これは、2022年度にコロナで中止となり、助成金を使用されなかったイベント(子ども会交歓大会・角島高齢者親睦会)の分です。
したがって、2023年度に豊北町の地域福祉に活用できるお金は
1,186,835円+435,670円+107,000円=1,729,505円
ということになります。すごい!地域の皆さんの善意で地域の福祉のためにこんなにもお金が集まるんですね!
豊北町の状況(助成計画)
集まった 1,729,505円 のうち、449,000円 が、今年度申請のあった 助成団体の活動 に配分されています。
この中には、わたしが会長を務める 豊北地区子ども会連合会の「交歓大会」や、地域の「朗読の会」「老人クラブ連合会」「民生児童委員協議会」などのほか、今年度の新規申請事業として、豊北小学校から「手話教室」の開催にかかる経費の助成が申請されていました。
そして、残りの 1,280,505円 が、社会福祉協議会助成事業 に活用されます。これは、豊北社協が主体となって行う事業に充てられるもので、福祉研修会であったり、「豊北地区ふれあい・いきいきサロン交流会」などの開催経費、社協だよりの発行など多岐にわたります。
(参考)社会福祉協議会事業について
参考までに、社協の助成事業の区分を以下に示します。5つに分かれていて、中でも地域福祉事業はさらに5つに分かれています。
・地域福祉事業
1 福祉員育成助成事業
2 福祉員活動推進事業
3 福祉活動備品整備事業
4 地域住民交流研修事業
5 福祉教育推進事業
・地域住民仲間づくり事業
・広報啓発事業
社協だより発行事業
・共同募金啓発事業
・地域住民居場所づくり事業
支え合い居場所づくり事業
最後の「支え合い居場所づくり事業」については後で別に紹介します。
赤い羽根共同募金の助成金を受けるには
さて、こんな感じで会議に出席しまして、赤い羽根共同募金について、少しずつ分かってきました。
で、これはもっと幅広く活用されても良いお金だな…とも思いました。
年間で170万円も地域福祉に使えるお金があって、助成団体の活動には50万円くらいしか使われていないし、助成団体も割と公的な団体というか、ゴリゴリの民間とか、市民団体とかからの申請が非常に少ない印象です。
福祉を目的とした助成金で、しかもその資金が募金なので、まずなかなか “市民団体の楽しいイベント” で助成金を申請しよう、という発想にはならないかもしれませんが、よく見てみると、意外と活用できるイベントって多そうです。
助成団体の活動
まず、助成対象となる活動の種別を見てみましょう。一覧表には以下の8カテゴリが挙がっていました。
- 地域から孤立をなくすための活動
- 子どもの生活と子育てを支援するための活動
- 障害者の地域生活を支えるための活動
- 高齢者の地域生活を支えるための活動
- 地域福祉の推進を図るための活動
- 災害対策のための活動
- 更生保護を目的とする活動
- その他緊急的な福祉課題を解決するための活動
どれも社会福祉の観点から重要な活動ですね。
いかがでしょう、みなさんが取り組んでおられる地域の行事・イベントって、上記のリストには該当しませんか…?
会議の中で実際にわたしが「こういう行事は申請対象になり得ますか?」と挙げてみたものは、社協の職員さんや理事に、「オォッ、そういうのいいですね〜!」と喰いついていただきましたよ。
例1:しめ飾りづくり交流
12月に、地域のお年寄りに、お正月のしめ飾りの作り方をレクチャーしてもらって、一緒に製作するワークショップ。日頃なかなか関わることのない世代間で、交流しながら過ごすことができる。お昼に食事を摂って、レクレーションなども行うことも可能。
→ 歳末たすけあい募金 からの助成の対象となり得る
あと、これは質問までしなかったんですが、同じように考えると、↓こういうのもアリっぽいですね。
例2:炊き出し訓練食堂
災害時に避難所に指定されている場所で、炊き出しの訓練を行う。豚汁やおむすびを作るシミュレーションを行うが、それを「地域食堂」のようなかたちで、地域住民に振る舞う。
参加者は、会場が災害時の避難所になることを確認できる。会場内に、ダンボールベッドや非常食など、模擬的に避難所を体験できるような展示を行ってアトラクションにする。
防災訓練を兼ねても有意義かも(初期消化の訓練とか)
下関の社協では、防災にもかなり力を入れているので、防災イベントを企画するととても喜ばれそうな気がします。いろいろ情報提供くださったり、講師派遣とかご協力していただけそう。
助成団体活動申請のネック
実は助成団体の活動を申請できるのは、各年度の4月とか、結構タイトな期間なんです。
これがなかなか新規申請が増えない原因のひとつになっています。
3月までに集まった募金を速やかに集計して分配しなければならないので、仕方のないことではあるのですが…。
市民団体などであれば、恐らく4月に「第1回定例会」的な集まりを催して、前年度の活動報告とか、決算・予算とか、役員の改選とか、そういう感じで「じゃぁ今年度も頑張りましょう!」って始まるところが多いと思うのですが、このタイミングで
「今年度こういうイベントを社協に申請して、赤い羽根共同募金の助成金を受けたいのですが…。こちらがイベントの概要、そしてこれがざっくりとした予算書です。この部分が助成金によって賄いたい経費です。なにか質問は…」
みたいなところまで仕上げて承認とって申請して…っていうのはなかなかレベル高いですよね。
なので、あらかじめ社協が、社協の事業として予算を計上しておいて、年度中に社協に申請があったものに対して社協から予算を分配する、という裏ワザを用意してくれています。
それが 支え合い居場所づくり事業 です。
支え合い居場所づくり事業 とは
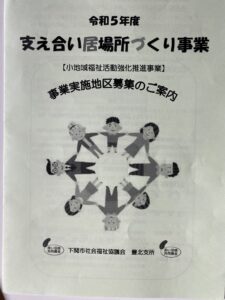
豊北社協が作成したパンフレットによると、支え合い居場所づくり事業 とは、
豊北町内にお住まいの方誰もが、地域で孤立することなく安心して暮らし続けられるよう、住民相互の交流や温かな団らんの場を提供し、支え合いの地域づくりの推進を図るため、活動の立ち上げを支援することを目的に実施するものです。
ということで、前年度の 赤い羽根共同募金 や 住民会費 を財源として、①住民相互の出会い・ふれあい・交流行事、②住民支え合い活動 を対象事業として募集しているものです。
ちなみに助成金額は1事業10,000〜60,000円で、毎年恒例の行事であれば最大3年間助成を受けることができます。
この事業が立ち上がった背景として、「豊北圏域 暮らしと福祉に関するアンケート調査(2020年)」によると、豊北町では
- 近所づきあいが「ほとんどない」と回答した人が1割
- 家族や親戚、友人とのお茶や食事の頻度が「年に数回以下」が約3割
- 家族や親戚、友人との外出の頻度が「年に数回以下」が26.8%
…という、胸を締め付けられるような寂しい現状が起こっているそうです。
そこで、このような方たちの温かい居場所となるような活動を募集し、助成します、というキャンペーンとして、豊北社協が事業としているものです。
ちなみにこれにも、わたしが「例えばこういう行事を計画しているんですが対象になりますか?」と質問した行事がありまして…
例3:専修寺マルシェ
そうなんです。すでに開催実績があり、今年も10月28日(土)に開催を予定しているイベントをブッ込んでみました。
この投稿をInstagramで見る
これはお寺の境内で、地域住民が農作物やバザーなどのお店を出したり、豚汁を販売したりして、キッチンカーにも来てもらったり、子どもたちの遊ぶコーナーを設置したりして開催した手作りのイベントです。
まさに住民相互の出会い・ふれあい・交流行事であるし、上記 豊北地区まちづくり協議会 妻崎会長のInstagram投稿にもあるように、(この時はコロナの影響で、ですが)「久しぶりにオシャレしてお友達にあえるわ」と言って喜ぶおばあちゃんが来られたり、支え合い居場所づくり事業 のコンセプトにもピッタリなんです。
そして、昨年度は 豊北地区まちづくり協議会 の全面的なバックアップのもと開催しましたが、要領をつかんだ2回目からは基本的には住民の皆さん主体でやりましょう、というのが まちづくり協議会 のスタイルですから、今回は予算面でもかなり苦労しています。
コンセプトよし、資金面での必要性あり、ということで、会議のあと早速 専修寺マルシェのリーダーに資料を見せて、「申請してみよう!」という方向になりました。
お問い合わせは、地域の社会福祉協議会へ
「募金の使い道」って聞くと、なんだか自分たちの生活とはあまり接点のない、なんなら発展途上国に学校を建てたり、子どもたちの予防接種になったり…ということを思い浮かべてしまいがちですが、赤い羽根共同募金は、地域福祉を目的として、わたしたちの生活しているまちのために使われています。
せっかくまちのために様々な活動をしているのであれば、より充実した活動のために、赤い羽根共同募金の助成を申請してみませんか?
申請したらなんでも必ず助成金を受け取れる、というものではありませんので、まずは地域の社会福祉協議会に相談されてみるのがよいと思います。
そして、お手元に小銭があるときは、お近くの赤い羽根共同募金や、歳末たすけあい募金の募金箱にぜひ入れていただき、より良いまちづくりに参加しましょう!