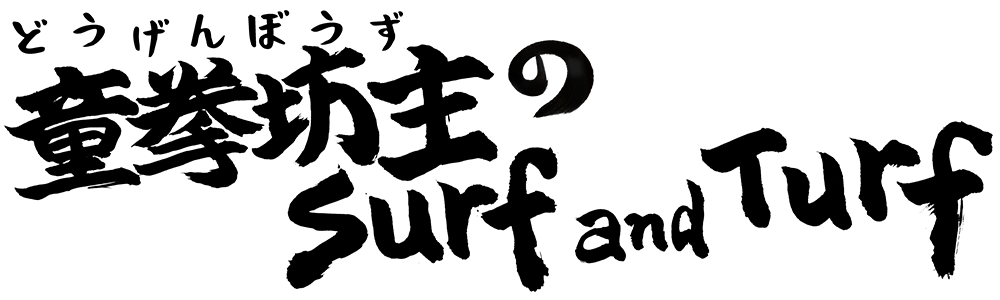意外と奥が深い まちづくりマルシェ論① 〜なぜわたしたちはマルシェをするのか

INDEX
マルシェ・フリーマーケット・バザー
最近、やたらと マルシェ 多くないですか?
ウチの まちづくり協議会 がやたらとマルシェやってるから、いわゆる カラーバス効果 で「マルシェ」って文字に目がいってしまってるのかもしれませんが…
そもそも「マルシェ」ってどういう意味か知ってますか?…まず何語でしょう?
そうです、フランス語ですね。
そして、意味は「市場」。英語でいうところの「マーケット」です。
今でこそ結構な割合で皆さんご存知の「マルシェ」ですが、40代のわたしにとっては、数年前までマルシェといったら
「カレーマルシェ」
一択ですよ。「マッシュルームが入った本格的な欧風カレー」だから…マルシェって…なに?キノコのこと⁇ マッシュルーム ⇔ マルシェ、響きも似てるし。
ぐらいのイメージ。
ましてや、地域の人がいろいろ持ち寄って出店するイベントっていってピンとくるのは
「フリーマーケット」
でしょ。ってか、ヘタしたら「バザー」。「バザールでござーる」とかすぐ言っちゃう世代です。
ちなみに「フリーマーケット」って英語表記した時は
Free Market
じゃないんですよ。「自由に出店できるマーケット」って意味ではありませんし、経済用語の「自由市場(Free Market)」に別の意味があるわけでもありません。正しくは
Flea Market
で、これももともとフランス語の「Marché aux Puces」つまり「ノミの市」の英語表記です。
なんでも、パリで、ノミのついてるような古着を売っていた市場が「ノミの市」と呼ばれていたのが元で、不用品などを持ち寄って売る市場をひっくるめて「フリーマーケット」と呼ぶようになったんだとか。
さらに調子にのってちなみアゲちゃうと、「バザー」は「市場」を表すペルシア語の「バザール」が語源だそうですよ。
…と、さて、いつもなら「イヤー、前置きが長くてすみません」と一言謝って、本題に入るところなんですが、この前置きを書き進めるうちに、アレッ?これってもうちょっと深掘りしといてもいいんじゃない…?と思い始めました。
だってね、冒頭紹介したように、ウチの まち協はじめ、日本中の団体がこぞって「マルシェ」って銘打ったイベントを開催してますが、たぶんその中の誰も「マルシェ」の定義なんて意識してないし、なぜ「マルシェ」をするのかっていう「マルシェ哲学」なんて毛頭ないし、カレーマルシェすら食べたことないと思うんです。
そこで今回は、なんで「マルシェ」をするのか?ってところを、わたしなりに考えてみて、それから次回、具体的なマルシェイベントを例に、その意味・意義や、取り組み方について考察したいと思います。
マルシェ的なイベントの文化
先に「マルシェ」や「フリーマーケット」、「バザー」といった、似たようなイベントのスタイルを紹介しましたが、他にもわたしが知っている限りでは、アメリカには「ガレージセール」とか「スワップミート」などもあります。
ガレージセールは、個人宅の車庫(ガレージ)や庭先に不用品を並べて販売する、個人単位のフリーマーケットのようなもので、
スワップミートは、フリーマーケットのように広い会場で、元々は古着や古道具の物々交換(スワップ)をすることを目的としたイベントでしたが、わたしが雑誌で見たものは、例えば古いクルマの中古パーツを販売するなど、特定のジャンルに特化した商品の売買が行われるものを指すことが多いようです。
アメリカって、子どもにビジネスを学ばせるために、軒先で自家製のレモネードを販売したりすることも一般的だったりするので、ガレージセールも含めて、個人で出店して、取引や交流を楽しむというカルチャーが根付いているように感じます。
また、少なくともわたしが実際に見た21世紀はじめの頃のアメリカやオーストラリアでは、古いクルマをレストアして乗る文化は残っていました。だからスワップミートも必要なものとして、自然な日常として溶け込んでいるはずです。
日本の「もったいない文化」とマルシェ
じゃあ果たして日本にそういう、ガレージセール的な「カルチャー」があるかな?と、「カルチャー」「文化」の切り口で考えてみると、わたしなりの解釈では、いまや世界レベルで「Mottainai」と認知されている「もったいない文化」はヒントになりそうな気がするんですよね。
子ども服が小っちゃくなっちゃったら「おさがり」したり、着物をリメイクしてバッグとか小物とか作ったり…。
なんだか、わたしが個人的に勝手に描く、昔からのステレオタイプな日本人の感覚 をイメージすると、「おさがり」とかリメイクって「不要になった『モノ』を無駄にしない」ってことが最優先であって、「売って生活の足しにしよう」とか「買いに来てくれた人と交流して楽しもう」っていうのは二の次のような気がします。だって「もったいない」でやってることだから。
だから、「おさがり」「お古」は家族や親せき、知り合いの範囲で解決できればそっちの方が気がラク、みたいな。
でも、一方で「バザー」は日本では明治40年頃から、売り上げを学校や教会の運営に充てることを主な目的に取り入れられ、広まったんだそうです。
それで バザーって今でも学校行事と併せてPTAがやってるイメージが強いんですね!
これも勝手に分析すると、家族・親せきや身近な範囲で処分しきれない不用品は、学校や教会など、「コミュニティのために」活用してもらいましょう、っていう文化は明治時代からあって、今も続いている。ってことは、日本人の文化にピッタリはまっているってことなんでしょう。
日本人の 和を重んじる教育。この善し悪しは置いといて、
「自分だけがいい思いをするのは忍びない」
「やるならみんなでやりたい」
「どうせやるなら誰かの役に立ちたい」
みたいなカルチャーの中で、個人宅で抜け駆け的に「ガレージセール」をやろう!っていうのは、特に田舎サイドでは勇気のいることです。
でも、地域の活性化のために数々のイベントを打ちたい、地域住民でなにかを成し遂げるという体験をしたい、和を重んじたい、っていう趣旨で、
海外に「フリーマーケット」ってのがあるらしいからやってみようよ!
って日本で始まったのがちょうどわたしの生まれた1970年代後半だったようです。
それから日本で独自にフリーマーケットのスタイルが確立され、これは完全に憶測ですが、
フリーマーケット(=蚤の市) っていうけど、ハンドメイド品とか飲食物とかも売ってて、これってむしろヨーロッパの「マルシェ」だよね…
って、海外ツウみたいな人が、まぁ当時のインフルエンサーみたいな人がボソッと言ったりなんかして、情報もインターネットで手に入るし、「ホンマや~ッ!」って勢いで「マルシェ」って呼び方が一気に広まったりしたんじゃないかな?
って思ったりもします。もしかしたら、それまで「スパゲッティ」って呼んでた食べ物を「パスタ」と呼び始めた時期とタイミング一致するんじゃないか…?くらいまで推理してますよ、わたしは。
ただ、最近の まちづくり の捉え方の大きな変化のひとつとして、「ボランティアでやってても続かない」っていうポイントがあって、わたしは非常に大切だと思っています。
働きかた改革とか、副業・複業とか、フリーランスとか、社会の変化も後押ししてくれていると感じますが、やっぱりこれからは「まちづくり でしっかり稼ぐ」って考え方は大切だと思います。
地域の特産品を活用して、これまでになかったビジネスを立ち上げる
とか、そういうことだってやれるんだぞ、っていうマインドセットに住民を、特に子どもたちを導くためにも、地域で行うマルシェやイベントに関わることで、地域にも自分にも利益がある、ということを学べる仕組みを考えていかなければならない、と思います。
これにはアメリカの レモネードスタンド や スワップミート の考え方も非常に役に立つのではないかな?
と、いうことで次回は、最近実際に豊北町で関わったふたつのマルシェイベントを振り返りながら、それぞれの特徴であったり、これから継続・発展していくためのアイデアを考えていきたいと思います。