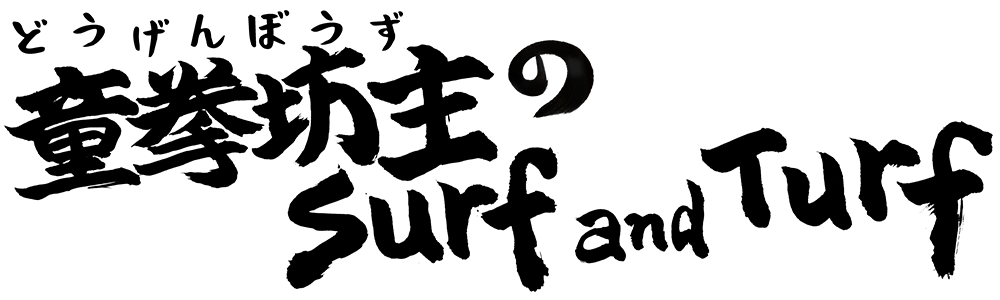下関市まちの魅力発掘プロジェクト 一発目「山口県下関らしさを考える・トークイベント」に参加しました!

INDEX
まちづくりを仕事に!と本格的に意気込み始めて1年以上経ってしまいました。
相変わらずバタバタと、日常の業務と家庭とまちづくりとの間で揉まれつつ、揉みしだかれつつ、最近ようやく少しずつ周りが見えてきたというか、進む方向が見えてきたというか…という感じです。
そんな中、この度「下関市まちの魅力発掘プロジェクト」というプロジェクトのキックオフイベントと言える「山口県下関らしさを考える・トークイベント」に参加しましたので、当日の様子を紹介したいと思います。
下関市まちの魅力発掘プロジェクトとは
2016年に市が実施した調査で
「地域に応じた都市機能が充実し、街のにぎわいや魅力があると感じていますか?」
という質問に対し、「はい」と答えた下関市民の割合は6.3%だったそうです。

コレは…どう受け止めるべきか。
だって実際、私も下関ってこの質問にあるような「都市機能の充実」とか「街のにぎわいがある」とか、そんなイメージからはかけ離れていると思います。むしろ6.3%の「はい」と答えた人に対して、どの辺りがその…?と突っ込んで訊いてみたいモンです。
それよりも、「はい」と答えなかった93.7%の市民のうち、どれくらいの人が “まだ諦めてない” のか、コレに非常に興味があり、大切だと思います。
日常生活の中で「下関はこんなじゃけぇ…」とか、「もうダメじゃし、しょーがないけぇ…」みたいな、終末的な、ため息まじりのセリフを聞くことって結構あります。
古き良き下関を知る世代の方に限って、こういう方が多い印象を勝手に受けていますが…。
そうではなく、現状を憂いて、おもしろきこともなき世をおもしろく してっちゃろーじゃないか!という晋作スピリットを持とーや長州男児、長州なでしこ!というワケで、(市の担当者さんが明確にそうおっしゃったワケではありませんが、勝手な解釈として)これを2019年には15.0%までグッと上げていきたい!というところだそうです。
この下関市まちの魅力発掘プロジェクトのコンセプトはズバリ「共創」ってコトで、行政・市民・民間企業が一体となり、エリア全体をひとつの経営体として捉えて、まちづくりの新機軸を築いていくという、なかなかに壮大でエキサイティングな取り組みとなっています。
あるかぽーとエリアの開発に星野リゾートが参画してくる!とか、そういう話です。
で、今回は、その一環として、D&DEPARTMENT PROJECT のシステムを活用し、d design travel という雑誌の関門海峡エリア版の発行に向け、ワークショップを展開していくコトになっており、そのキックオフとして、D&DEPARTMENT PROJECT 代表 ナガオカケンメイさんをお招きして トークイベントが開催された、ってコトですね。

ナガオカケンメイさんとは
D&DEPARTMENT PROJECT 代表の ナガオカケンメイ さんは、18〜35歳の間はグラフィックデザイナーとして活動されましたが、環境問題について考えた時に、デザイナーが環境破壊の片棒を担いでしまっていないか、ということに気付かれたそうです。デザイナーが新しいものを創り続けることで、古くなったデザインが廃棄されていく。
そして「長く続いていることは個性である」という視点に立ち、ロングライフデザイン(Long Life Design … 和製英語)という考えから、「新しく作らない」、「デザインしないデザイナー」という、これまでの「デザイン」「デザイナー」という概念を超越したスタンスで様々な取り組みをされています。
d シンボルに込めた願い
D&DEPARTMENT PROJECT は、「プロジェクト」と冠するだけあって、さまざまな取り組みをされています。
d&department
その土地に長く続いているものを紹介するショップを作っているプロジェクトです。
d47
各都道府県に長く続いている品を紹介・販売するプロジェクトです。たとえば…
・d47 musium
渋谷ヒカリエに開設されているデザイン物産美術館
・d47食堂
d47 musiumに併設されたレストランで、「美味しく正しい日本のご飯」を提供しています。
…といった取り組みが d47 のプロジェクトとして進められています。
d design travel
その地域に実際に滞在して「いつの時代にも変わらない定番に、最新のものを組み合わせること」こそ「センスが良い」というスタンスで、地域の魅力的なポイントを紹介している雑誌です。
今回のトークイベントに続いて7/6(土)を皮切りに開始される3回のワークショップは、この d design travel の海峡エリア版を発行するためのワークショップになります。
私は日程の調整をモタモタしていたら最初の参加申込み締切りに間に合わず、残念ながら落選してしまいました…!
d design workshop
ロングライフデザインの観点から地域の魅力を再考し再発見するワークショップ。山口県はこのワークショップへの参加が非常に積極的で参加者数もハンパないのだそうです。
事例として静岡の廃校を活用したミュージアムなどが紹介されました。

骨格標本が学童机に着席していたり、ホルマリン漬けがオシャレに展示してあったり、一部の写真を見ただけでも、ブッ飛んでいるうえにどこかノスタルジックっていう、なるほどコレぞセンス…!と頷ける事例でした。
トークイベント前半を終えて…
前半の講演ですでにワシづかみにされた感じです。
ロングライフデザインの考え方は、ミニマリスト的な考えに通ずるものも感じます。
「ずーっと変わらない リーバイスの501が好き。コレばっかり穿き続けたい」
「流行りすたりではない、無印良品のオーガニックコットンの白いシャツは着ていて気持ちがいい」
「Tシャツと言えばヘインズのビーフィTシャツでないとタフに生きていけない」
「結局のところ 男子の下着は 綿100% のふんどしにとどめをさす」
私は身の回りの持ち物のほとんどに、こだわりを語ることができます。
ロングライフデザインは、こんなミクロなこだわりを、地域レベル、国レベルまでマクロ化したもの…と一言では表現できないんでしょうけど、近いものがあるんじゃないのかな…と感じました。
というワケで、トークイベント後半のワークショップ編へと続きます。