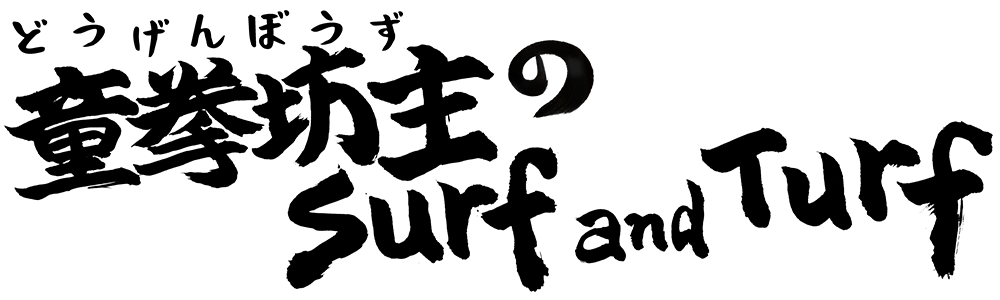谷上プロジェクト in 下関 第2弾!「下関市豊北町で地域のリアルな課題と可能性を探る講演会」に参加しました。
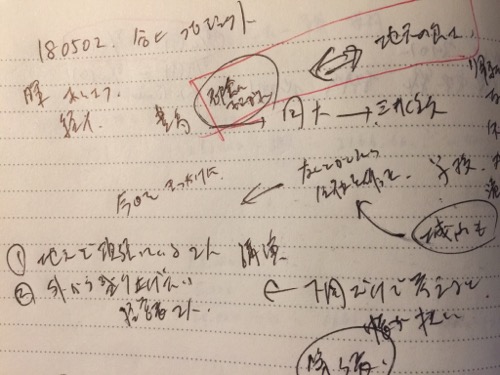
INDEX
- 海耕舎 新名文博さんの講演
- 百姓庵 井上雄然さんの講演
- オマケ:森脇のダンナのダメ出し
- ChatWork 山本敏行さんの講演
- 株式会社ペンシル 覚田義明さんの講演
- 借金2,000万円、口座残高600円から始まったペンシル
- 株式会社ペンシルのストラテジー
- ペンシルの考える地方活性化のビジネスモデル
- ペンシルが勝ち続けているワケ
- 外貨を獲得してくるという考え方
- 今の時代だから可能になったダイレクトマーケティング
- ホームページ製作から、ホームページコンサルティングへ
- この夏は「ペンシルアカデミー」でライバルに差をつけろ!
- 質問①:覚田さんの講演について、「外貨獲得」と言っても、講演では「国内向きに物を売る」という段階で完結している。日本の市場は小さくなっていくが、それだけで良いのか。
- 覚田さん
- 山本さん
- 質問②:インバウンド観光団体の受け入れが重要という。最近下関に接岸した大型クルーズ客船から75台のバスが出てきたが、下関に来たのはたったの1台で、残り74台は県外に出て行ったと聞いた。下関を観光して、下関にお金を落としてもらうにはどうしたら良いか。
- 質問③:まちづくりを考える、行動を起こす時に、「意識の低い人」をどのように巻き込んだら良いか
- まとめ
- 良い会でした!
最近すっかり熱を上げてしまっている、すっかりお熱な、谷上プロジェクトの御一行が、再び豊北町にやってきました。前回、発症した時の記事がこちら↓
谷上プロジェクト出る杭が出過ぎて抜けて下関までやってきた!ChatWork 山本さんとあのヒカルが…!! (2018.3.19)
備忘録 谷上プロジェクト ChatWork 山本さんとの会話から「地元を客観的に見ること」 (2018.3.24)
谷上プロジェクト自体については、↓この辺りからいろいろ発信されています。
今回は「下関市豊北町で地域のリアルな課題と可能性を探る講演会」ってことで、最近流行りの、イベントタイトルを見ただけで内容の概要がイメージできたり、見た人の興味をそそって参加を煽ったりするタイプのイベントです。
豊北町生涯学習センター、かつて合併前は「町民センター」と呼ばれていました。私のやっていた「豊北町ジュニアリーダーズクラブ」という、子供会のお世話をするボランティアの拠点にもなっていた懐かしの施設です。その2階会議室を満席にし、イベントはスタートしました。
ちなみに参加者の内訳は、小学校のPTA関係や商工会青年部の繋がりで知り合った方もおられるし、地域の意識高い系住民の皆さんが大半という感触でした。そして私の隣りにはヒカルの親父さん、私流に呼ぶなら
「森脇のダンナ」
が息子の様子を見守り、その後ろには森脇のダンナのお兄さんご夫婦、つまり
ヒカルの伯父さん伯母さん
も来られているという状況でした。
(ヒカルの伯父さんが、このブログの読者さんということがわかったので、贅沢に行を使用してご紹介しており・まァ〜ッス!!)
まずは主催者、ヒカルのご挨拶
いきなりヒカルが登場です。
このイベントの概要を、自己紹介を交えて話します。

都会に憧れて地元を離れ、都会的な暮らしを手に入れるほどに地元の良さに気づかされた、という、私に似た経験の持ち主です。
彼は帰省するたびに「何かが失われていく」ふるさと をなんとかしたいという気持ちで、はたから見れば順風満帆な銀行員の立場を捨て、会社を興し、今日に至っています。
彼は今回この講演会に、
① 地元で頑張っておられる方 お二人
② 外から盛り上げたいというアイデアを持っておられる方 お二人
の4名の講演者に講演をお願いしています。
ヒカルはこのイベントを「良いお話を聴けた」というだけで終わせたくない!という思いで、②の2名の講演者を数日前からお招きし、①の2名の講演者の経営する施設等でキャンプやマリンスポーツ、塩作りなどの体験をしていただき、この地域の良さや現状、今後に向けた課題等を肌で感じていただいたそうです。
海耕舎 新名文博さんの講演
講演のトップバッターは、株式会社 海耕舎 という会社を興された、元•競艇選手であり、かつて私も一緒に海に入ってサーフィンをしていたこともある 新名 文博 さんです。

サーフィン•角島との出会いからNPO法人設立
新名さんは元々レース中の事故で負ったケガのリハビリとして取り入れたことがきっかけでサーフィンをされるようになった、とは知りませんでした。
角島大橋が開通した頃に出会ったサーフィン。いつも入っていたコバルトブルービーチで毎年のように海水浴客が水難事故で亡くなっている悲しい現状。
新名さんは大好きな角島の海で悲しい思いをする人が出て欲しくないという気持ちから、サーファーを中心にライフセービングを行う団体を立ち上げます。
「ただ人命が助かれば良い」ではなく、救助された方が必ず社会復帰できることを目指し、ファミレスで夜間にミーティングを行うなど経費を節約しつつ、専用のボードやAED、ジェットスキーなどを揃え、5年がかりで「渚の交番」というコンセプトで日本財団に支援を申請し、ついに補助を獲得します。
補助申請を通じて気づかされる、地域が直面する様々な問題の解決に向けた取り組みの課題!
それは漂着ゴミの清掃や水産資源の減少といった「海」に直結する問題だけでなく、高齢化社会対策や耕作放棄地、空き家対策などまで幅広いものだそうです。
海耕舎の様々な取り組み
現在、海耕舎は角島大橋の本州側付近、島戸というエリアに「渚の交番」を建設中です。この島戸地区だけでも空き家が50件以上あるそうで、空き家対策の取り組みは、拠点にも角島にも近いこの地区から開始され拡がっていくのでしょうか。
また、角島大橋周辺で大量に発生するムラサキウニが海藻を食い荒らすことで、この地区の貴重な水産資源であるサザエやアワビが減少の危機にさらされています。これを救うために、海耕舎ではムラサキウニの駆除も行なっています。
この取り組みのユニークな点は、駆除のために捕獲したムラサキウニも研究し、定期的に駆除を行うことでウニの若返り(?)が起こり、味が改善されるそうです。これをうまく活用し、海耕舎によって期間限定でオープンされていた「島戸テラス」で「うにく丼」というメニューを考案・提供していたそうです。
さらに新名さんはムラサキウニの殻にも注目し、ウニガラ専用のバイオトイレを1基設置して、ウニガラを使用した堆肥を作り、豊北高校(現•下関北高校)の協力のもと耕作していた有機農園で活用することも考案しました。
海耕舎の提供するアクティビティ
現在海耕舎は、ホテル西長門リゾート の敷地内で様々なアクティビティを提供しています。
拠点の代わりに設置してあるトレーラーハウスの周辺ではキャンプができ、サーフィンだけでなくSUP(スタンドアップパドルサーフィン)やクリアカヤックなどのマリンスポーツ、水上サイクリングやバナナボートも体験できます。詳しくは 海耕舎HP や、以下のFacebookページをご参照ください。
興味深いのは、バナナボートやジェットスキーを行う際にも、速度規制エリアを設けて、漁業の妨げにならないよう配慮されていることです。
古くから漁業をしてきた地区に、全く他所から巨大な資本がやってきて、生活をメチャクチャにしてしまう、という話はありそうですが、循環型社会の実現を目指す 海耕舎 ならでは、角島でサーフィンをしていた頃から現地の漁協の方とも繋がりのあった新名さんならではの取り組みに期待せずにはおれません。
今後の課題
海耕舎の抱える悩みは人不足だそうです。
アルバイトを雇おうにも、交通の不便な場所なので、自動車等の「足」がなければ勤務はなかなか現実的でないという状況です。
また、ビジネスとして利益を上げる必要はありながら、できるだけ安くサービスを提供したい、と考えると、海耕舎が一身にその努力を背負ってビジネスを構築していくのではなく、行政やスポンサー、NPO等の協力も巻き込みながら「コレクティブ インパクト」を起こすことも考えておられます。
百姓庵 井上雄然さんの講演
今回のイベントに向かう車の中でたまたまテレビのローカルな情報番組が流れていて、百姓庵の紹介をしていました。
プーチン大統領が来日し、長門市で日露首脳会談が開催された際のディナーで、井上さんの作られている「百姓の塩」が使用された、というものです。
すごいな…と思って聞いていたニュースのご本人にその直後にお会いできるとは!改めてヒカルが導いてくる繋がりパワーの強さを感じます。
井上さんは4つのキーワードで、ご自身の取り組みを紹介されました。
食品問題
講演者の井上雄然さんは下関市の出身で、食品を扱う商社にお勤めだった時に「食品業界のウラを見た」のだそうです。「これが良いものだ」という食べ物を作りたい!という気持ちから農業を始められました。
環境問題
環境問題を語る井上さんの言葉の中で「有限の地球の中で、無限に経済を成長させようというのは無理がある」というのが非常に印象的でした。甲本ヒロトの「地球は何人乗りだ」という詞や「海まで山分けにするのか」という詞を聞いた時に似た衝撃です。
宙に浮いた都市
“天空の城ラピュタ”のイラストが映し出され、井上さんが東京に住んでおられた頃に台風の直撃を受けた時のお話が紹介されました。東京のような大都市、日本の首都であっても、台風がひとつ上陸すればバスが止まり、タクシーも宿も取れず、あっという間に帰宅難民で溢れてしまいます。この時井上さんは自宅まで4時間半を歩いて帰る羽目になったそうです。
結局、人間の築いた文明も、自然の力にはかなわないわけで、人間は地に足をつけて生活することが正しいのだ、と気づくきっかけとなりました。
文明中毒
井上さんも、もちろん私も、生まれた時に既に電気やガスが当たり前にありました。
イヤ…厳密に言うと、私の古い記憶では、私が幼い頃、私の実家は五右衛門風呂で、土間で薪をくべて沸かすスタイルでした。それが次第にガスと薪のハイブリッドになり…現在はオール電化に太陽光発電…と進化を遂げているのですが、それでもやはりその時その時の「ワッ、便利になったねェ…!!」という感激は次第に薄れ、「あって当たり前」という生活にドップリ慣れてしまっています。
ここに井上さんは警鐘を鳴らします。都会に生まれた子供は、大人になる前に1度は、例えば発展途上国の生活などを体験させておくべきなんじゃないの?と。
これはもしかすると、豊北町の出番かもしれません。
塩作りから百姓庵への変遷
井上さんは、15年前に塩作りを始められました。まずは塩作りにもっとも適した土地を探して、ハイエースで日本中の海岸線を回られたそうです。
その結果、下関出身の井上さんが辿り着いたのが、下関市のお隣、長門市だったという、灯台下暗しも甚だしいお話ですが、私はこれって本当に素晴らしいことだと思います。
「近いし、ここで良いかな?で長門市!」、と「全国回って、結果、長門市!!!!!!!!」ではその意気込み、説得力、自信、ビックリマークの数、全て違ってくると思います。「よくぞ長門市に良ェ場所があってくれたな…!!」と、そこにあったドラマに気づき、勝手に熱く感激してしまいます。
百姓庵ってどんなところ?
百姓庵は、長門市西部に油谷湾を形成する向津具半島の先っちょ、地図で見ると私は線香花火の先っちょを思い浮かべてしまう 俵島 というエリアにあります。
2002年2月に築100年以上の古民家のリフォームを始めた頃は、かつての私の実家と同様、五右衛門風呂がついていたそうです。これが今では岩風呂になり、バーカウンターも設置されています。
現在のショップは元々牛舎だった建物だそうで、Before & After を、写真と現地で見てみたいですね…!!
様々な体験もでき、お米づくりワークショップ では、エネルギを使わず、人力による作業にこだわっておられるそうです。
“それじゃ耕せないよ…”ですって?
「耕さないお米作り」というスタイルもあるそうです。「泥んこ田植え」というパワーワードも飛び出し、田んぼの中でシンクロナイズドスイミングをしているような“パワーフォト”も映し出されました。苗を放って田植えをするなど、遊び心を持った農業へのアプローチのようです。
そのほか、百姓塾、アースガイド、海の清掃活動、森の清掃活動、トマト栽培、水耕栽培…世界中から居候を受け入れたりもしておられるそうです。実際に長門市に移住されている方もおられ、HPを拝見したところ、スタッフの方にも居候を経て移住を決意され、百姓庵に所属されている方を発見しました。
百姓庵HPは コチラ です。(泥んこ田植えに異常に反応してしまった方は コチラ を!)
そしてFacebookページもコチラに
「百姓」という言葉の持つ力強さ
つい最近まで、「百姓」という言葉は放送禁止用語でした。田舎では昔から日常的に用いられているので意外に思われる方もあるかもしれません。私も、2002年頃MSNのチャットをしていた時期があって、その時に「百姓」というハンドルネームの方がチャットルームに入って来た、と思ったら、巡回しているMSNのスタッフに強制的に退出されていたのを見たことがあります。違うハンドルネームに変更して戻って来たその人が“「百姓」ってハンドルネームが不適切なんだって”と発言したのを見て驚いたことを覚えています。
そもそも「百姓」という言葉には「百の仕事ができる人」という意味があり、あらゆる仕事をかけもちでやっている人を指しているそうです。時代によっては、差別的な扱いを受けていたライフスタイルだったのかもしれません。
井上さんがスクリーンに映し出す写真が、芋の畑の白黒写真に切り替りました。よく見るとバックには国会議事堂が写っています。これは戦後間もない頃の写真だそうです。井上さんの言葉をお借りすると、「この時代の日本人が持っていた たくましさ を取り戻したい」とのことです。このたくましさがあったから、戦後 日本は驚異的なスピードで復興できました。しかし残念ながらこれは現代の若者には引き継がれていないような気がします、と。
これは既に私にも耳の痛いお言葉です。
たくましく、百の仕事ができる人材であらねば…!!
百姓庵の理念
現在、長門市には相当な広さの農地がありますが、農業従事者は2,000人程度であり、しかも高齢者の占める割合が高いです。そのため20年後には人口減少に伴って農業従事者数は200人まで減少する可能性があり、そうすると農地や農産物の消費者も減少し、害獣被害対策などのひとりあたりの負担は急激に増加することになります。
このような大きな流れに対策を講じるにも、ひとりでは限界があります。
そこで井上さんは仲間を増やすことにしました。
「Company」つまり会社という言葉の語源は「共にパンを食べる仲間」だそうです。「それでは、共にパンを食べる仲間を見つけて会社にしよう」ということで、井上さんは2017年に百姓庵を法人化されました。
法人化すると、仲間でやりたいことをなんでも事業化できます。
例えば「美味しいトマトが食べたいね」ということになったら、「トマト事業」を始めて、ネット販売やトマト作り体験や…技術指導、加工品製造、販売…とどんどん拡大していくことができます。
これを実現するため、百姓庵の定款には、ありとあらゆる業種が盛り込まれ、どんな事業も立ち上げ、展開できるようになっています。農業や製造業から…あまりにもたくさんあったのでひとつずつご紹介できませんが「ビール醸造」なんてのも含まれていました。麦とホップを栽培して地ビールを醸造することも、手順を踏めばできるわけです。
ところがそんな中、今度 百姓庵 の仲間になる予定の方は鍼灸師なのだそうですが、定款に医療は含まれていなかった…だそうです。
井上さんの百姓庵が目指しているのは「複合型経営 × 異業種コラボ」まさに未来を切り開く百姓スタイルです。
オマケ:森脇のダンナのダメ出し
ここで一旦「リラックスタイム」というコトで、ヒカルから休憩が呼びかけられました。
ガタガタと席を立ち、会場から外へ出る人たち…を見ながら、森脇のダンナが「イヤイヤイヤ…」とつぶやきます。
休憩挟むんなら 「○○時○○分から次を始めます」って時間をアナウンスせんとダメやろ〜
そりゃそうです。実際、休憩がなんとな〜く終わり、ゾロゾロと、次第に第2部が始まる…という雰囲気になってしまいました。
うやぬゆしぐとぅや ちむにすみり = 親の言うことは 心に染めなさい(沖縄民謡「てぃんさぐぬ花」より)
ChatWork 山本敏行さんの講演
ここからは第2部ということで、下関•豊北町を外から見て、盛り上げるためのアイデアを提供してくださるお二方の講演です。
ChatWork CEO の山本敏行さんは、冒頭にもリンク張っていますが、
谷上プロジェクト出る杭が出過ぎて抜けて下関までやってきた!ChatWork 山本さんとあのヒカルが…!! (2018.3.19)
備忘録 谷上プロジェクト ChatWork 山本さんとの会話から「地元を客観的に見ること」 (2018.3.24)
このように既に私は少しだけ交流させていただいていて、その考え方や人柄、オーラ的なものについては肌で凄さを感じています。
今回、この会場に来られて、生の熱い講演をしていただける予定だったのですが、急遽仕事の都合で来られなくなってしまいました。
ただ、来られない = 講演できない ではなく、今の時代、インターネットとアプリがあれば、東京からでも豊北町で講演できてしまいます。
しかも、その為に使用するアプリというのが「ChatWork」、山本さんの会社で開発したワークチャットアプリってんですから、どんだけですか!って話です。
チャットワークについていきなり興味を持った。詳しく知りたい!って方は チャットワーク(ChatWork) 日本語サイト ←こちらをチェック!
Facebookページもコチラに

これは、おそらく豊北町初となる、チャットワークのビデオ通話機能の実験でもあります。
この後、時々映像が止まったり、音声が不安定になったりすることが時々ありましたが、それでも数秒程度で、講演の妨げになるほどではありませんでした。
谷上プロジェクトとは
山本さんが発起人となり、「なんでもある」「なんでもできる」のになぜか閉塞感を感じる現在の日本を、ワクワクする国に盛り上げよう!というコトで、神戸市の谷上地区に注目し、
「谷上を日本のシリコンバレーに!」
をコンセプトに、
- 失敗は成功のもと
- 出る杭を伸ばす
- 大ボラ吹き大歓迎
という理念のもと、様々な活動をしているプロジェクトです。
我らがヒカルは、このプロジェクトによる谷上への移住者第1号であり、彼の興した 株式会社レストレーション も谷上に登記されています。
3つの理念から勇気がもらえる
日本社会の持つ「失敗は許されない」「出る杭は打たれる」「揚げ足を取られる」っていう雰囲気の、いわば真逆を声高に訴えている 谷上プロジェクト の存在は、「前例がない」とか「会議のための会議」といった言葉に個性を阻まれ、押さえ込まれている人に勇気を与えてくれます。
シリコンバレーでシノギを削り合っている人たちは、たとえまだ成果が上がっていなくても、「オレは世界を変える!!」「1ヶ月でユーザー500万人達成する!!」と大風呂敷を広げ、それに向かってひたすら動きます。それで失敗した時、日本で想像される周囲の反応は「ホレ言わんこっちゃない…」「だからやめとけって言ったのに…」でしょう。
ところがシリコンバレーでは「ちょっとその失敗シェアしてくれ」「なにがダメで失敗したんだ?」だそうです。他人の失敗からも学ぶことがたくさんあるし、皆が大きな目標に挑戦しているんだから、それが日常茶飯事なわけです。そしてその中に「次はここをこんな風にやったらうまくいくんじゃないか?」というような、助け合い、励まし合いといった、仲間同士の友情や愛情が感じられます。
どちらの社会が良い、ということを決定したいわけではなく、日本中の「変化を起こしたい」と強く思っている人たちが谷上に集まり、そこで切磋琢磨し、谷上イズムを加えた個性を持ち帰って地元を盛り上げる。これが次第に少しずつムーブメントとして成長し、結果として日本中が盛り上がっていくイメージでしょうか。
なぜ谷上?
私たちは、既に谷上でスタートしているのを知っているので、その理由として聞けば「なるほど〜」って納得するのですが、「さァ、オレたちのプロジェクト、ドコで興す?」っていう時期に、全国でもっともポテンシャルの高い街としてよく谷上をピックアップすることができたな…!!と思います。
谷上は、神戸市営地下鉄で、新神戸駅からわずか1駅、神戸最大の繁華街三宮から2駅という近さでありながら、夏になると川に蛍が舞う、自然の豊かな街なのだそうです。駅ビルには空き店舗スペースが多く、神戸市内でありながらこれからまだまだ変化の余地を有しています。
また「集まりやすい街」でもあります。これはもちろん先述のとおり地下鉄のアクセスが良いですから、JRや新幹線で人が「集まりやすい」。
三宮から南下していくとポートアイランドの沖に神戸空港があります。これで全国から航空機で人が「集まりやすい」。
また、神戸空港からベイ・シャトルという船でさらに南下すると乗船時間約30分で関西国際空港にアクセスできます。これで世界中から人が「集まりやすい」。
この視点は実は画期的で、関西エリアについて考えるとき「阪神」のように、東西でネットワークをイメージすることは多いですが、谷上から関空まで、南北でネットワークを捉え、その利便性について言及しているのはコロンブスの卵的発想です。
「なんにもないところですよね?」と揶揄される谷上。しかし谷上駅の駅舎に、Googleのストリートビューでも確認できるほど堂々と掲げられた「新神戸まで8分 三宮まで10分」のコピーのとおり、10分でなんでもある三宮に行けるんです。この良さに気づかない方には…「まだ○○で消耗してるの?」と…(ry
谷上プロジェトのスタート
神戸市は「住みやすい街」として 日本1位 、アジア2位 、 世界4位 というランクを誇りながら、若者離れの著しい街だそうです。このことは神戸市の「若者に選ばれるまち」というスローガンにも表れています。
そんな中で、山本さんが興した「谷上プロジェクト」はキックオフイベントを開催すれば200名定員のところに280名集まり、神戸市長が「自分の選挙イベントより人が集まってる…」とボヤくほどで、谷上ツアーを企画すればあっと言う間に満員になってしまうなど、目に見えるかたちでもかなり注目されています。
「谷上が賑わえば、シャワー効果で三宮も賑わう」
という山本さんの目論見には、先述の神戸市長だけでなく、兵庫県知事、谷上駅長など、多くの方が期待を寄せています。
既に12月だけで6社が谷上地区に登記し、移住者も続々集まってきています。
谷上プロジェクトが考える地方創生とは、「外から地方に連れてくる」ではなく、「地方から谷上に人材を送り出す」、そして谷上でそんな人材同士が出会って化学反応を起こし、地元に還元する、という仕組みです。
森脇ヒカルという分かりやすいモデル
谷上プロジェクトを説明するのに絶好のモデルが今回の主催者、ヒカルではないでしょうか。
長州を盛り上げんとする現代の志士、維新の風、時々語尾が「ぜよ」などなど…とにかく熱い。
ヒカルと出会った山本さんは、彼の体育会系照英キャラ(に “惚れ込み” と表現すると語弊があるかもしれないしなんだかシャクなので)を “イケる” と感じ、2017年に「長州は一旦置いておいて、まずは谷上にフルコミットしてやってみないか」とスカウトします。
この時ヒカルはメガバンク法人営業5年目のバリバリ銀行員でした。「5年間はキッチリ勤めてから地元に帰ろうと考えていたところだった。だから谷上で修行するにしても、半年後からならできる」と 社畜全開 お世話になっている銀行に仁義を通したいとする気持ちを山本さんに伝えますが、山本さんのスピード感覚では半年後なんて遅すぎます。「そりゃ残念、他を当たる」と、お話は決裂してしまいました。
ところが…
その3日後、10月のアタマにヒカルから山本さんに連絡があります。
「銀行から、上海への転勤辞令が出ました」
半年後に「5年間勤め上げた」という形で銀行を辞め、地元に帰ろうと思っていたら、来月から上海に行かなくてはならなくなった。
なんてドラマチックで運命的な話なんでしょう。かくしてヒカルはいよいよ半年前倒しで銀行を退職する決心をし、すごい勢いでコトを進めました。「退職に伴い10月末には社宅を追い出される」ということで、谷上プロジェクト初の谷上移住者となります。
ヒカルの会社 株式会社レストレーション も谷上に登記し、いよいよ谷上プロジェクトの一員、一国一城の主となって、谷上駅ビルの暖房のない薄暗いオフィスで、ダウンジャケットを着て、ポツンと置かれたデスクに向かっている写真がスクリーンに映し出されると、会場内に笑いが起きました。
ただ、ソレはあくまでネタの部類であって、実際に現在ヒカルがやっていることは、谷上地区に切り込んで行く隊長です。
- 飲食店のリピーターになる(飲食店が少ないから必然的にそんな風になってしまう傾向はある)
- 地域の行事に積極的に参加する(防災訓練やお祭りなど)
- 老人クラブのカラオケや写真クラブに参加する(お婆ちゃんにモテるため、氷川きよしを練習中)
などなど、彼のキャラクターがあってこその打ち解けっぷりが想像できます。
一方で地元下関で山口銀行の主催する「次世代経営者クラブ」の松井会長と谷上プロジェクトを通じて繋がり、2018年3月には、同クラブの勉強会で講演することになります。これが先ほどから何度もリンクを張っている、
谷上プロジェクト出る杭が出過ぎて抜けて下関までやってきた!ChatWork 山本さんとあのヒカルが…!! (2018.3.19)
こちらの記事の一件となるワケです。
この時の一連のイベントの中で、ヒカルは前田下関市長とも繋がり、また会社は谷上に登記しているにも関わらず、次世代経営者クラブに入会できてしまいました。
ここで山本さんの発した言葉こそが谷上プロジェクトの真髄です。
「もし森脇ヒカルが半年前、谷上プロジェクトに加わらず、彼の当初の計画どおりに進めていたら、2018年3月のこの時点では、まだ銀行で働いていたということです」
今、グングン注目を集めている谷上プロジェクトに山口県からコンタクトがあった場合には、山本さんはヒカルを紹介します。ヒカルひとりで、下関でやっていたら、次世代経営者クラブで講演をするまでどれだけの時間と苦労を要するでしょう。市長と同じステージに立つまで、会場をいっぱいにするイベントを主催するまで…。
谷上をとおして、日本を変える!
それは、第2、第3の森脇ヒカルを、全国各地につくっていくことに他なりません。
豊北町を盛り上げるアイデア
最後に、山本さんが豊北町に実際に来てみて浮かんだアイデアは
「都会ではできない子育て」に特化したまちづくり
だそうです。
都会で子育てをすると、公園で安心して遊べない、自宅でもスマホばっかり…というような、なんだか窮屈なイメージがありますが、山口県と言えば「松下村塾」「総理大臣の輩出日本一」といった、教育に良いイメージがあります。
このイメージを現実にするために、例えば小•中学校では豊北町で夏休みに長期間のサマーキャンプをやります!というような、ノビノビ遊んで豊かな人格形成を促すようなプログラムを作ります。
これはまさに先述の 海耕舎 や 百姓庵 とガッツリコラボして、充実した内容を練りに練る、と。
そして、田舎の町でこういった自然と触れ合う系の企画を作った時に、最も苦労するのがその周知•広告なのですが、豊北町の強みは、「すでに集客できていること」です。何万人も来る海水浴客にサマーキャンプの告知ができれば、その効果は期待できます。
サマーキャンプでグングン伸ばした子供たちは、高校ではどうしますか?
ヒカルは山本さんに母校である 豊浦高校 の話をよくしていたようです。
ヒカルの在校時は男子校で、ゴリゴリの体育会系。ランニングシャツの体操服で命を賭けて燃える体育祭!修学旅行ナシ!やたらと強い愛校心!前田市長も次世代経営者クラブの松井会長も豊浦高校出身!
高校はビシバシ鍛えるスパルタを売りにしたらどうでしょう?入学時、保護者に「なにがあっても文句言いません」と承諾書を書かせるくらいのスパルタ!
これはすごいブッ飛んでいるようにも聞こえますが、確かに今の時代には希少なスタイルです。
一度俯瞰して考えてみると、よく内容を詰めれば、受け入れられそうな気もしてきます。事実、ヒカルも他の卒業生も、振り返って「楽しかった」と口を揃えているわけですから。
株式会社ペンシル 覚田義明さんの講演
最後の講演者は、株式会社ペンシル の 覚田義明 会長です。
3月の谷上プロジェクト御一行“ご来関”の時に、UZUハウスで行われたイベントの動画を観て、なにかただ者ではない感がヌワァ〜ンと出ていて、強烈なインパクトを受けました。
しかし恥ずかしながら私は覚田さんのことも株式会社ペンシルのこともよく知っておらず、今回が初めて触れる覚田さん、となりました。
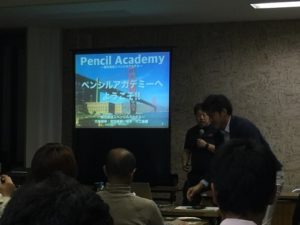
最初にヒカルが覚田さんを紹介したんですが、ココでヒカルは覚田さんの講演の「ツカミ」の部分と、「主題」の部分をサラッと盛大にネタバレさせました。
それでは、そのツカミからいってみましょう。
借金2,000万円、口座残高600円から始まったペンシル
覚田さんは28歳の時、社長から任された会社が倒産してしまいます。
いきなり2,000万円の借金を抱え、口座の残高が600円という極貧状態に…!!
覚田さんは問いかけます。
「皆さん、口座に600円しか残ってないって、どういうことか分かりますか…??」
コレは、ATMで現金を引き出そうにも、1,000円単位でしか引き出せないから、600円のお金を下ろすためにあと400円も必要という、まさに どうにもならない 状態なんですね…。
死にたい気持ちになるほど落ち込んでいた覚田さんは、1,500億円の借金を抱えた人に会いに行きました。どれだけ悲惨な生活をされているのか…。
すると、1,500億円というもはや想像もできない借金を抱えたその人は、意外にも明るく楽しく生きておられたそうです。それを見た覚田さんは、一気に気持ちを切り替えて、1995年に、6畳1間の部屋で「ペンシル」を設立します。これまで関わったことのない、インターネットの会社です。
実は1995年というのは、私が高専に入学した年で、インターネットに出会った年でもあります。「“www” とは “World Wide Wait” の略だ」っていうジョークもあったあの頃、既にインターネットのビジネスを立ち上げておられたっていうのは、やはり感覚がド鋭いんですよね…。
私はその頃「“IBM” とは “I Blame Microsoft” の略だ」っていうジョークすら理解できませんでした。
この後、ペンシルは 営業をかけなくても福岡の企業からコンサルティングの依頼が舞い込む企業へと成長を遂げていきます。

株式会社ペンシルのストラテジー
順調に成長を続けるペンシルですが、2000年に覚田さんは「地方の限界」を感じます。
でも、福岡はヒトもカネも増えてる大都市ですよね…?
このカラクリについて覚田さんは、福岡の周りの県から人が来ているだけで、そこに人が増えているワケではないと分析します。福岡には結婚相手のいない女性が多いという状態で、男性がいない、と。
優秀な男性は皆、東京などのもっと大きな街や海外に流出してしまうし、残っている男性は、まァ、ちょっとアレで、結婚もしない。
カネについても、豊かなのは街中だけで、郊外に出ればどんどんバスの本数が少なくなったり路線がなくなったりしている状況で、実は福岡県だけを単体で見ると「仕事がない」「物価が高い」…お金が引き金で起こる負のスパイラルに陥っている。
これではどんなに良いサービスを開発しても、福岡では広告も打てないよ!というワケです。
ペンシルの考える地方活性化のビジネスモデル
地方活性化には明確なビジネスモデルが必要、というのが覚田さんの持論です。ではその明確なビジネスモデルの骨子になるのは…? それはブランド戦略です。
ブランド戦略…「ブランド」…それだけで価値が見出されるものですね。
覚田さんが例として挙げられたのは、
- ノーブランドだけど本革のバッグ5万円
- ブランド品のビニールのバッグ 20万円
ハイッ、売れるのどっち?
Bですね。LとVを組み合わせたマークがいっぱいついてる茶色いビニールのバッグなら、20万円でも売れるんです。
逆に、聞いたことすらない人が作った本革のバッグには、5万円「も」出したくない。
ネームバリュー、知名度、先入観…いくらモノが良くても、それだけでは売れないってコトなんです。
地方でブランド戦略を考えるとき、元々そこにあるものでなんとかしないといけない、という方向に走りがちです。
確かに…。豊北町を特産品で盛り上げる…特牛イカか!よーし透き通るイカのお造りで…と思ってしまいます。でも必ずしもそうではない。
例えば覚田さんの故郷 福岡の特産と言えば 辛子明太子 ですが、コレは「北海道のスケトウダラの卵」に「釜山のキムチ」をベースにした味付けを施したもので、福岡原産のものは入っていないんです。
ただ、辛子明太子の元祖とされる ふくや が、その作り方を広くシェアしたことで、多数の明太子メーカーが誕生し、「福岡と言えば辛子明太子」というブランドが確立したワケです。
地方創生 → ブランド戦略 という流れの中で、ここ下関で 辛子明太子 を例に出された覚田さんはさすが…!! と思います。
実は、「辛子明太子は下関が発祥!!」という説もあり(恐らく旧・下関市街を中心に未だに根強く残っているのではないか…という気がしますが)、下関は商売がヘタだったがために、見事に福岡に持っていかれた、というものなんですね。呼子のイカは特牛沖で獲られたイカだ…という話があったり、ココに下関もっとブランド戦略頑張ろう!というメッセージも感じます。
ペンシルが勝ち続けているワケ
覚田さんは、ブランド戦略のキモとも言えるキーワードを3つ、紹介してくださいました。
- これしかない
- ここしかない
- 今しかない
です。例えばこの時覚田さんが手に持っていた Volvic のミネラルウォーター。日本でも100円で変えます。
これを「ハイ、500円で売ります!」と言われても、買う人はいません。だってその辺のスーパーで100円で買えますからね。
ところが同じ Volvic のミネラルウォーターでも「コレは本当にフランスの採水場で汲んだものをそのままボトルに詰めたもので…」とか「採水場にもランクがあって、コレはフランス国内向けの採水場で取られた非常に貴重なもので…」とか、上記のキーワードを意識させるキーワードを盛り込んで宣伝されると、なんだか500円出してでも飲んでみたくなりませんか?
ペンシルも、基本的にはこの原理で、とにかく研究に研究を重ねて、強烈なキャッチコピーとどこにもない商品を打ち出し、今日まで勝ち続けていると言えます。
そのキャッチコピーというのが、
売上げが上がる 研究開発型ウェブコンサルティング会社
で、実は中身より先にこのキャッチコピーが出来上がったのだそうです。
その後で徹底的に、どうやったら売上げの上がるウェブサイトを創れるのか本気でやった、と言うのです。この「本気でやった」で全てを語っているのが実にニクくて、私たちはそれだけを聞いて、血ヘドを吐くまでの想像を絶する「本気でやった」も可能性の中に秘め、覚田さん率いるペンシルの研究開発セクションがやり抜いた「本気でやった」のレベルに想いを馳せるワケです。
かくしてペンシルは、キャッチコピーに恥じない実績を着実に積み重ねていきます。ペンシルの仕事により、それぞれの販売サイトにおいて、某生活消費財大手は2年間で売上げ10倍、某お菓子メーカーは4ヶ月で売上げ21倍を達成します。まさに「キラーサイト」。消費者に訴えかけるウェブサイトの作り方を「本気で」研究しアゲた成果です。
(脱線:中国地方では「〇〇しアゲる」と言い、関西では「○○し倒す」と言います。例)シバきアゲる vs シバき倒す)
かくして6畳1間から始まり、覚田さんが自身のデスクにつくためには部屋の真ん中に陣取る会議用テーブルの下に潜り込まなければならなかった 株式会社ペンシル は、今やオフィスの中にジャングルや神社を備えるオフィスを構え、年間500人が見学に訪れるほどに大きくなりました。
外貨を獲得してくるという考え方
福岡で生まれたペンシルですが、現在福岡の顧客は全体に対して僅か1%なのだそうです。
意外と福岡で利用されていないペンシル…!!
ただ、ここにも覚田さんのストラテジーが輝いています。
例えば今、あなたの住んでいる地区に1件のパン屋さんがあり、年間1億円を稼いでいるとします。
これはパン屋さん単体では1億円を稼いでいますが、地区全体で見れば、結局地区の中だけで1年かけて1億円というお金がグルッと回っただけで、地区全体の経済は発展していないんですよね。
そこにもう1件パン屋さんがあったとして、コレはネット販売や地区外の大きなレストランとも取引があり、同じく年間1億円を稼いでいるとすると、このパン屋さんは街の外から1億円を獲得してきていることになるワケです。
このように、外から持ってきたカネを地区の人に分配する、という考え方は、現代の地方創生には非常に重要です。
今の時代だから可能になったダイレクトマーケティング
先述の「外貨を獲得してくる」という考え方は、インターネットがこれだけ普及した現代の世の中で実現したものです。
インターネット以前の時代、商売人はまず「地域ナンバー1」を目指したものです。まずは口コミで、「あそこの○○は良いよ…!!」という実績を作ったうえで、今度は県内、地方、全国…と地道に続いていくステップを踏んで段階的に成長してきたものです。
ところが現代においては、インターネットを活用することで、最初から日本中、ひいては世界中の、自身の商品に興味を持ってもらえる相手を探すことができます。
極めて単純に考えると、地域=山口県の人口が143万人で、これが一気に全国=1億2千万人を相手に勝負できるということになると、実に90倍近く売上げが上がるという計算になるわけなんです。
この、口コミなどに頼らない、コンシューマーひとりひとりに直接はたらきかける手法が「ダイレクトマーケティング」であり、情報社会における最新のマーケティングです。ダイレクトマーケティングを行うということは、全国47都道府県全てに店舗を持っているのと同じことです。
ホームページ製作から、ホームページコンサルティングへ
先述の辛子明太子の ふくや は、商品のインターネット販売も行っておりましたが、売上げは伸び悩み、半年間で3個しか売れていない、という状況でした。
そこでIT関係各社にコンペ参加を募り、インターネット販売促進するためにどうしたら良いか、コンペが行われました。
このテーマに対し、覚田さんが出した答えは「辛子明太子をネットで販売するのを辞めましょう」でした。
そもそも生物の明太子、単価は1,000円でしたが、ひとつ発送するのに送料が800円かかってしまうのだそうです。1.8倍のお金を払ってまで買いたい!という人は、半年で3人しかいなかった、ということです。
コンペに参加していた他社が、あくまで「どうやったら売れるか」を必死に考えてきた中で、ひとり冷静に「売れませんよそんなモン」と言ってのけた覚田さん。コレをきっかけに、ホームページ製作から「ホームページコンサルティングをやろう!」と決意し、ふくや には全く新しい手法を提案します。
それは、「テストマーケティングキャンペーン」と題し、ふくや のホームページで、明太子50個プレゼント!という企画を行うものでした。偶然にもこのタイミングが ふくや の創業50周年に重なり、「50周年を記念して 辛子明太子の ふくや が 明太子を50個プレゼント!」というインパクトのあるキャンペーンは反響を呼び、5000人からの応募があったといいます。
また、年代別に辛子明太子の購買に結びつく条件を調査したところ、以下のような結果が出たそうです。
| 40〜50代 | 20〜30代 | |
| 塩分 | × | ○ |
| 着色料 | ○ | × |
| 添加物 | ○ | × |
| 価格 | 1,000円 | 2,000円〜3,000円 |
| ネット販売 | × | 送料込みなら○ |
この結果から覚田さんは、20代〜30代をターゲットに、無添加・無着色、プレミアムでちょっと贅沢な辛子明太子を開発し、ネット販売するというアイデアを導きだします。
これは典型的な「キラーサイト」の成功事例です。
この夏は「ペンシルアカデミー」でライバルに差をつけろ!
さぁ、ここまでの「どうだ!」だけで終わらないのが覚田さんの面白いところ。
このペンシルの実績、研究に研究を重ねた成果を惜しみなくシェアし、皆さんも「売れるWebサイト」が作れるようになる「ペンシルアカデミー」ってセミナーがあります!
受講すると「売れるサイト」が作れるようになる!
ペンシルアカデミー Web講座、今日の講演会に参加している皆さんは特別に入会金無料!
受講料も通常50,000円のところを今日はなんと特別に9,800円!!!!
受講の申し込みはWebで!特別価格適用のためにはチラシのコードを入力してください!!
コードの有効期限は今日から3日間!
すごい!今すぐ申し込まないとものすごく損してしまう気がする…!!
これでさらに「お友達紹介で商品券プレゼント」とか言われたらイッちゃってたかもしれんな…。
かくして怒涛の勢いで覚田さんの講演は幕を下ろしました。
株式会社ペンシル のHPは コチラ!
そして、Facebookページもこのとおり!
質疑応答
それぞれの講演が非常に面白く、あっと言う間に時間が過ぎたようでしたが、時間が押しておるとのことで、質疑応答の時間はちょっとだけ、ということになりました。

質問①:覚田さんの講演について、「外貨獲得」と言っても、講演では「国内向きに物を売る」という段階で完結している。日本の市場は小さくなっていくが、それだけで良いのか。
大学生からの質問でした。外国生まれ外国育ちとのことでした。コレに対する覚田さんの答えは、
指摘のとおり、国内市場は縮小傾向にあり、ペンシルもグローバル戦略を進めている。今回の講演のポイントは、「とにかく“地域ナンバーワン”を目指す、というアプローチをやめよう」という点にあった。
ということでした。
ここで「せっかくだから」ということで、覚田さん、山本さんに「豊北町の感想」をお話いただくことになりました。
覚田さん
- 土砂降りの中キャンプをしたが、朝、テントから出ると角島大橋が見えた。写真で見たものを実感・体感できることが現地に行く良さ。
- 海の潮と潮のぶつかる所(海士ヶ瀬?)に驚いた。海の中に川があるようだった。あれを活用してトライアスロンをしてみたら面白いかもしれない。
この「海士ヶ瀬でトライアスロン」っていうアイデアには会場がザワザワしました。
「一番あの流れが強くなるのはいつ?冬?じゃぁ冬に!」
まさか「危険」を売りにブランド戦略が立てられるとは…!! 目からサザエのフタが取れた気分です。
「トライアスロン」っていうのは実は私も考えたことがあって、スイム1.5kmは角島〜本州でできそうです。バイク40kmで海岸線を走り、最後のランで滝部まで。滝部温泉を復活させて、ゴールした後は入浴してもらって、休憩・宿泊も可能、というものです。
山本さん
- 下関には韓国の方が多いことに驚いた。韓国は就職難と聞いている。韓国の方が働ける環境を作ってみるのはどうか。
- 地域を盛り上げるためのイベントは単発で終わっては良くない。「地域サービス商社」を設立して地元の人を配置し、利益を上げるという方法もある。
- 谷上プロジェクトについて、神戸市役所には続々問い合わせが寄せられている。豊北で成功実績を作り、全国に第2、第3のヒカルを作っていく。「森脇暉をよろしくお願いします」。
最後はもうヒカルの応援演説になっちゃいました。
質問②:インバウンド観光団体の受け入れが重要という。最近下関に接岸した大型クルーズ客船から75台のバスが出てきたが、下関に来たのはたったの1台で、残り74台は県外に出て行ったと聞いた。下関を観光して、下関にお金を落としてもらうにはどうしたら良いか。
下関は海外から来た場合に換金が不便、世界各国の電子マネーに対応していない、など、受け入れ体制自体が整っていないことも事実。かつて騒がれた「爆買い」は、現在中国でも日本に来ずともインターネットで商品が手に入るようになり、「爆買い」が来日の目的ではなくなってきている。
「日本に行きたい」ではなく、ピンポイントで「下関に行きたい」となる目玉を作ることが必要。
自動的に下関にお金が落ちる仕組み、も考えられる。例えば角島大橋も市外の方からは通行料を取る、クルーズ船が長州出島から出てくる時に人数分の通行料を取る、など…。
質問③:まちづくりを考える、行動を起こす時に、「意識の低い人」をどのように巻き込んだら良いか
団結力が大事。「意識高い人」で集まって、グループに名前をつけて、とにかく活動する。対立している人は1人ずつ説得していく。
結局は「人」。「誰がやってるのか」で判断されるもの。
ヒカルを盛り立ててスターにする。そして「ヒカルがやってるなら…」で動く人を増やしていく。
この「周りの巻き込み方」は非常に参考になりました。
私も地元の行事に首を突っ込んでいますが、いつも変わり映えしないメンバーで、大半は父親よりも年上で、ヘタしたら私の祖父を知っていたりする世代だったりして…。
また少し、自分の進むべき方向、進みたい方向が見えてきた気がしました。
まとめ
井上さん
こういう会を1回やっただけでは何も始まらない。指を掲げて、止まってもらう。仲間を作る。
ヒカルが来たら一緒にやる、来なくても勝手にやる、というくらいの積極性、行動力が大切。
新名さん
例えば福岡流のまちづくりをマネして豊北町でやってみる、というのはナンセンスだが、谷上プロジェクト流、というのは有効だと思う。これまでの歴史の中で、「人が減っていく」というシチュエーションは初めてのことだから、とにかく大風呂敷を拡げて、その中に残ったものをやっていくイメージ。まちおこしを格好良くやっていきたい。
山本さん
まず動かなければ何も始まらない。今日の会で「良い話を聴いた」で終わらないこと。
「森脇暉を囲む会」をヒカル自身が企画し開催するので、「森脇暉をよろしくお願いします」。
覚田さん
今でこそ会社は他の人に任せて、月に1度程度しかオフィスに行っていないが、かつてペンシルが潰れそうになった時には、信頼できる方の話を聴き、2時間くらいの会話で聴いたことを会社で全部やった。そのうえで、コレはできた、コレはできない、コレはできるけど自分たちに合わない…というのを選択し、自分たちのスタイルを創った。とにかくやる!すぐやる!が大切。
吉田真次 下関市議会議員 の総括
今回の講演会では、ずっと豊北町の中にいると気づくことのできなかった事に気づくことができた。またその一方で、地域に住んでいるからこそ分かることもある。
ヒカルは大学の後輩でもあるので、これからも頑張っていただきたい。
森脇暉の最後のあいさつ
森脇暉を囲む会、必ずやる。
今日の講演会で配付したアンケートを回収・集計し、質問には応えて、違う形のイベントを2ヶ月以内に開催する。
良い会でした!
本当に熱い、良いイベントでした。
ヒカルは本当にお疲れ様でした。
私にとっては、とにかく動かないといけない、と思うきっかけになりました。
仕事があるから、家族があるから、で、なんとなく本気で向き合えてなかったズルい自分自身が見えて、恥ずかしく思いました。
とにかく仲間を作って行動を起こして、対立する人たちを根気強く説得していくことで、自分たちがマジョリティになってしまう、という覚田さんのお話が、モヤモヤしていたものをスッと下ろしてくれた気がしました。
田舎での暮らしを満喫しよう、せっかくだから楽しもう、というのが今の私のライフスタイルの基準ですから、「家族を犠牲に」ってつもりはないんですが、プライベートな時間を活用して、最大限やってみたいと思います。