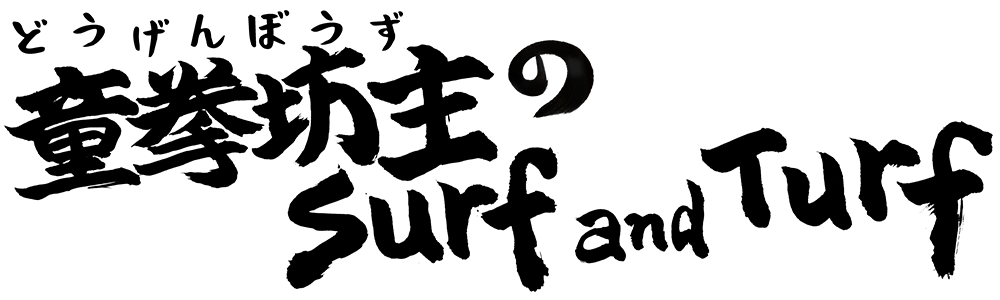下関市消防防災学習館「火消鯨」を見学。2つの偶然が重なって、息子も大興奮の貴重な体験ができました!
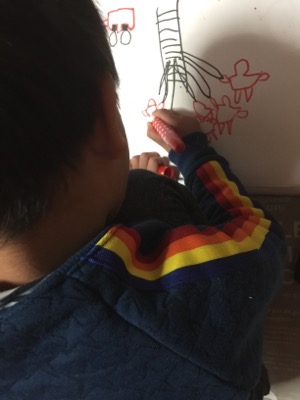
INDEX
6歳になった息子の将来の夢は「消防官」。
保育園で参加した消防出初式で見た 梯子乗り に感激したらしく、家でもその時の絵を描いています。
下関市には 下関市消防防災学習館「火消鯨」 という施設があり、下関市中央消防署と同じ建物内に、消防に関する体験ができるほか、タイミングが良ければ勤務中の消防官が消防車両などを紹介してくれます。
仕事の関係で何度か行ったことがあり、息子も喜ぶに違いないと思ってこの度行ってみました。
まさにベストタイミング!
先述の「タイミングが良ければ」消防車両を紹介してくれる、というのは、こう言ってはアレですが、ド直球で言ってしまえば、要は“ヒマな時”でないと対応してもらえない、というコトなんです。
管内で火災があって今まさに出動ォ!!って時に、「あの〜、見学…」ってムリですよね。
そこは承知の助で行かなければなりません。あくまで本業優先。
それを息子に言い聞かせて、こんにちは〜って受付を覗くと…オォ、“マー”!!
なんと知り合いの消防官、私は“マー”と呼んでいますが、そのマーが受付にいたのです。私はマーが消防官になる過程に少しだけ関わっていました。
息子が消防官を夢見ていて今日は見学に来たことを告げると、マーは防犯カメラの映像をチラッと見て、
「今日は滅多にないチャンスですよ!」
と力強く言いました。
なんでも、今日は車両の車庫の建物の窓を清掃する日で、業者が高所作業車で来ているので、その間消防車両は全て車庫から外に出ているとのこと。消防車の前に高所作業車が停まって窓拭き作業してたら出動できませんもんね、コレはラッキー!!
午前中は、建物の屋上で火災を想定した訓練も行われていたそうで、その時間帯だったら対応はアウトだったかもしれません。窓拭き作業で車両が全部外に出たタイミングでやってきた私たち、しかもちょうどマーが受付、強運です。
事務所にいる消防官の方に受付を代わってもらって、マーが車両を案内してくれるコトになりました。
出動準備室
消防服の並んだ出動準備室に入らせてもらいました。
出動!となったら隊員はココで消防服を着て飛び出して行くそうです。

そう思った矢先、出動準備室の内線電話が鳴り、マーが応答します。
別の署の管内で火災が発生したそうで、出動要請があるかもしれない、とのことで、残念ながら車両案内はできませんね…ということになり、マーは出動に備え、私たちは受付に戻って施設内の見学や体験をすることにしました。
しかしそれは消防隊員が出動するところが見られるわけで、それはそれで貴重な体験になるな…!!
すごいな、ドキュメンタリー番組みたいだ!と思っていたら再び出動準備室の内線が鳴り、どうやら今のところは出動しなくても良さそう、という雰囲気になりました。
車両案内はできそうですよ、とのことです。
しかしいつまた状況が変わったり、新たな出動要請が飛び込んでくるかわかりません。出動準備室から外に出て車両案内を始める前に、マーは消防服を着用しました。
車両案内中に緊急出動があったらそのまま出動できる態勢になっていなければならないそうで、いつも緊張感のある職場なんだな…と実感しました。
それでは車両を見学させてもらいます
建物の外に出ると、この時期には珍しく良い天気で、消防車両の赤と空の青のコントラストが美しいです。
息子もマーに甘えて抱っこしてもらいました。お相撲に抱っこしてもらうと…ではないですが、なんだかパワーがもらえそうです。

はしご車
様々な消防車がありますが、やはり圧倒的な存在感を放っているのは はしご車 です。
息子が「ビルの12階(10階と言ったかな…?)まで届く…」と呟いたのをマーが聞いて「そう、よく知ってるね!」と驚いていました。

息子は運転席にも座らせてもらいました。
ドアを開けると、ステップがせり出してきます。
そこに立って、私も写真を撮ってもらいました。

これだけ消防車両が並んでいると、大人もテンションが上がります。
本当に良いタイミングで来れたな…と実感しました。

救助工作車
消化するホースやポンプがついていない消防車両もあるんですね…!
コレは 救助工作車 といって、レスキュー隊員が乗り込んで出動し、火災現場や災害現場で救助活動を行うための道具がたくさん積んであります。チェーンソーやデッカいハンマーや、様々な長さのロープやカラビナなどの連結具や…。どの道具もピッカピカに磨かれ、整然と収められていました。

“中央3”
息子が最も興味を持ち「乗りたい」と言った消防車両が 下関中央署3号車 でした。無線で連絡するときに「中央3から本署へ…」みたいな言い方をするのだそうです。
最も出動機会の多い車両だそうで、息子がマーに抱っこされている写真でいうと左から2番目です。
「いかにも消防車」というスタイル・サイズの車両で、「歴戦の勇士」といった雰囲気が出ています。
「将来もし息子が消防士になったら、一番よく乗る車両だろう」という、そういうところに息子が興味を持ったのなら大したもんだな…と思いますが、実際はどうなんでしょう。
隊員は後部座席に乗る、と聞いて、後部座席に乗せてもらいました。マーが息子に「火事くさいだろ?」と訊いています。頭を車内に突っ込んでみると、確かに焦げくさいにおいがします。本当に数々の現場を乗り越えてきたんだな…!! と感動しました。「しょうぼうじどうしゃ じぷた」を彷彿とさせ、私も「中央3」に愛着を感じます。
ちなみに後部座席の背もたれの後ろには酸素マスクのようなマスクがつけてあって、消防官は現場に到着するまでに車内でマスクを装着するのだそうです。

支援車
最後に大きな「支援車」を見せてもらいました。マーと息子のジェスチャーでその大きさを表現しています。
この支援車は、中は大きな部屋になっていて、被災地などに派遣された消防官の宿舎としても使用されるそうです。広場などに駐車して、中央のふたつ窓が付いた部分をズズズッと横に引き出すことで、さらに広い部屋ができるとのこと。キャンピングカーのバケモンですね。
息子が「ジュースとか はこぶ くるまみたい」と言いました。コカコーラの車に見えたようです。
それを聞いたマーも、コカコーラのトラックとすれ違ったら、一瞬“アレッ!?”と反応してしまう、と話していました。消防官あるあるかもしれませんね。

ひととおり消防車両を見せてもらい、何人かの消防官さんにも声をかけてもらって、息子も感激したようでした。
マー、忙しい勤務中にありがとうございました。
火消鯨 館内の見学
シアター
防災について映画で学ぶことのできるシアターがあります。
「大人向けと、こども向けの「あさりちゃん」とがありますが…」とスタッフの方がおっしゃるので、
「下関らしく魚介のキャラでアニメでも作ったかな?しかしキャラ名がパクリっぽいけど…」
と思いながら、こども向けをリクエストしました。
小学校の1クラスくらいは入りそうなシアターを、親子で独占です。
間もなく映画が始まり、テロップに「原作:室山まゆみ」と表示されます。
「“あの”「あさりちゃん」か!パクリどころじゃなかった…!」
と瞬時に気づく70年代生まれ。

(写真を撮って良いものか…ダメかもしれない…)
懐かしの あさりちゃん が現代風にアレンジされて、災害への自宅の備えについて家族で話し合います。
息子も飽きることなく終わりまで鑑賞しました。
上映後、スクリーンの前に置かれた非常食などをチラッと見て、次へ進みます。
初期消火体験
消火器を使用した、火災の初期消火を体験できます。
スクリーンに映し出されたストーブに、洗濯物が落下し、引火します。
合図に合わせて水消火器を手に取り、正しい手順で消火に当たります。
開始前にスタッフの方からいわゆる「ピン・ポン・パン」の消火器の使用手順と、消火器のホースは炎に向けるのではなく、燃えている「もの」に向けることを教えてもらっているので、正しい手順と方法を練習できます。

防水のスクリーンにセンサーがついているのか、正しい位置に放水し続けると火が小さくなり、ちゃんと消火できると「消火成功!」のような表示が出て、息子も満足そうでした。
火災時の避難体験
煙が充満した暗い部屋から避難する体験もできます。
避難するときに気をつけなければならないこと「お・は・し・も」を問われ、息子が正確に答えていました。「押さない・走らない・喋らない・戻らない」です。
家族が火災現場に取り残されたら…! …戻るな…やっぱり…。
体験者の年齢や希望に合わせて、照明の暗さを調節できるようで、真っ暗闇の中を2つのドアを通って避難、ということもできるようです。
今回はお子様モード。

うっすら見えるので、息子はハンカチを口に当て、スイスイと進んで行きます。
本当は壁伝いに進んだり手探りでドアノブを探したりすることの困難さを体験するものだったのでしょうけど…。
しかし実際の火災現場では、壁やドアノブが熱されて ゥァチッッ!! みたいなコトはないんでしょうか。
そもそもそこまで熱くなるほど火の近くだと絶体絶命なんでしょうか…。
展示コーナー
この日は 平昌オリンピックで、展示コーナーに入ると、壁に設置されたテレビで 羽生結弦 が男子フィギュア フリーの演技をしているところでした。
それはさておき、展示コーナーには被災地などで使用されるダンボール素材の避難所キットや、非常食、防災グッズなどが展示されていました。

あり合わせの段ボールで避難所の間仕切りなどを作っていると思っていましたが、最初からキットになっているものもあるんですね…!自治体ごとに購入されているそうです。

ノスタルジックな消防車や制服などの展示もありました。
消防署+火消鯨、片方ずつでは正直少し物足りないかもしれませんが、両方見学できるとかなりの充実感です。小学校の社会見学旅行に来たようでした。