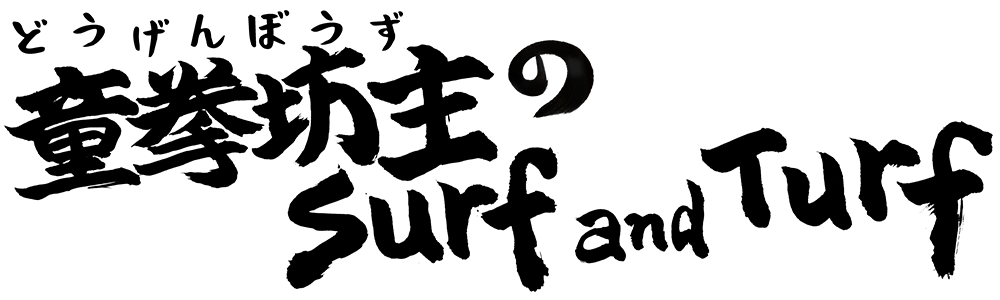11/25 第2回 豊北地区まちづくり協議会ワークショップに参加しました。今回のテーマは「新しい高校」と「つぶれた温泉施設」の活用!

INDEX
豊北地区まちづくり協議会のワークショップ、今回で第2回目となります。
第1回目の様子はコチラ
「世代を超えて意見を交わす。9/23 豊北地区まちづくり協議会 ワークショップに参加しました。」
新設高校の説明会に出席
今回のワークショップの第1部は、今度、近隣の高校がふたつ統合し新設される高校の説明会からスタートしました。豊北地区にあるほうの校舎を使用して新設されるのですが、高校の特色やコースについての説明がありました。
個人的には、すごく中途半端な印象を受けました。
良くも悪くも、田舎の平均的な高校というイメージです。
制服まで、男子はフロントジップタイプの詰襟で、隣町にあった水産高校の「ネイビーのフロントジップの詰襟」という硬派なものでもなく、いかにも進学校という白ランでもなく…黒というかチャコールグレイというか…。そして女子は襟がセーラー服で前の留め方がブレザーという、もはやここまでくると「徹底した中途半端」という域です(あくまでも個人的な感想です)。
オィサンらが集まって「こりゃ良ェトコ取りで万人受けするに違いない、コレにしよう」と頷き合っている様子が目に浮かびます。

前回のワークショップでは、新設される高校では県内・県外からも生徒が集まるような魅力を!潰れた温泉施設を寮に!といった、フンワリしているもののエキサイティングな話が出ていましたが、説明会でスライドに表れる高校はもしかして別の高校…?というくらい無難。
無難がイチバン!
無難で何が悪い!
という天の声が副音声で聞こえる感じ。
そしてそれをできるだけエキサイティングなPowerpointの資料にしてみました、面白いでしょ!?ねぇ面白いよね??
と言わんばかりのプレゼンターの先生のドヤ顏が虚しい…。

ウーン…決して悪くないのよ。公立だし。奇をてらっちゃダメなんでしょうよ。
責めてはいけない。
きっと、素直な良い子は育つでしょうけど、私だったら、こんな高校じゃ物足りないな…。入学したとしたら、なんとなく3年過ごして、なんとなく進学して、なんとなく他所に就職して、なんとなく社会人生活が始まって、特に思い入れのない地元には定年まで帰って来ない。
地域がいろいろ仕掛けて、地域の高校生を盛り上げる!ってくらいでないと、生徒の愛校心・アイデンティティが育まれないんじゃないかな…という気がしました。

例えば、ビーチクリーンとマリンスポーツ。
こんな年に1回くらいの体験をそんなデカい声で言われてもね…。ドコでも手を変え品を変え、そのくらいのコトしてるでしょうよ。
例えば思い切ってマリンスポーツ系の部活があります!
サーフィン部があったって良いんじゃないかしら。
在学中に船舶免許が取れる部活とか、スキューバダイビングのライセンスも取れるとか。
ただしソレを実現するには外部のコーチや監督が必要ですよね。高校だけではやれない。
ジビエ料理研究会は毎週末、猟友会の罠の見回りを手伝っています!
分けてもらった肉を調理し、釣り同好会の魚料理と腕を競い合っています!法的に販売はできないので部員しか味わえない贅沢な味です。
…とかね。
地域住民は、新設高校のそういうトコに積極的に関わっていきましょうよ!という意見はどうかな?
…と、言うばっかりで結局今のところ人まかせな私の意見なんですが。

コミュニティスクールとしての側面も持ちます!
ほうほう、コミュニティスクールとな…。
「コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条の6)に基づいた仕組みです。(文科省HPより)」
図や説明で、なんとなくイメージは湧きますが、具体的にどんな仕組みが構築されるのか…上手いコト回転していくのか…。
いずれにしてもコレは本当に、地域住民が他人事と思わず関わっていこうとしないと、コミュニティ・スクールなんて絵に描いたモチに終わるでしょうし、制度どころか高校も消滅しちゃうんじゃないかしら。
裏を返せば、住民が本気出せば、いくらでも面白いアイデアを高校に反映させて、特色ある高校を創り上げるコトができる、というコトでしょうか。
私たち世代が踏ん張らないといけませんね。
それにしても制服は今からでもどうにかならんもんかしら…
地元の現役の中高生に意見聞いてみたんだけど「アレ選んだ校長のセンス最低」ってコトになってますよ(あくまでごく一部の若者の個人的な感想です)。
たぶん選んだのは校長先生じゃないぜ…。
温泉施設の視察
今回のワークショップでは「新設の高校をいかに盛り上げるか」と「潰れた温泉施設をどう有効活用するのか」がテーマになっているので、高校の説明会に続いて温泉施設の視察を行います。
居酒屋・食堂的なスペースだったところ
山の上に建つ新館と、1段低い位置にある本館の2棟が廊下でつながっている温泉施設の新館側にあったスペースです。
自治会の行事の後で飲食しに来たことがあります。
サッシから見晴らしの良い屋上に出られるので、その様子を視察しました。

飲食スペースはテーブルに置かれた備品に埃を被った新聞紙がかけられ、廃墟感が漂っています。

厨房だったところも生気を失っています。
宿泊室だったところ
宿泊施設だったので、客室もあります。1室1室はとても広くて、旧き善き時代の温泉宿です。
宴会場だったところ
宿泊客を取らなくなってからも、しばらく日帰り施設としては営業していたので、私の実家ではここで法事などの会食をしたことがあります。
田舎では近所や親戚のお付き合いで会食の機会が多いので、貴重な施設だったと思います。
宴会場前のカウンターで発見
宴会場の前がロビーのようになっていて、簡単なカウンターが備え付けられていました。

披露宴などが行われた時にはウェルカムドリンクなどを提供していたのでしょうか…と思って中を覗くと… 
ンッ?
「シモラク牛乳」?
コレは知る人ぞ知る 細かすぎて伝わらないネタなんですが、アニメ映画「新世紀エヴァンゲリオン」の 庵野秀明 監督は山口県出身で、作品中に山口県ゆかりのアイテムがチラッと登場することがあります。

「しもらく牛乳」ね?
現在は社名は「やまぐち県酪」になってますが、牛乳配達の「しもらく牛乳」ブランドは残ってるのかしら…?
キャラクターの「ベルちゃん」は「そよ風ヨーグルト」のパッケージなどでも見ることができますね。
廊下
客室の並ぶ廊下は幅が狭めです。床もフカフカで、良い意味でノスタルジック。

スナックだったところ
かつては自治会の飲み会などの2次会でカラオケしに来ていました。
くたびれたソファがさらにくたびれて横たわっています。コレもノスタルジック。
フロントだったところ
日帰り入浴の券売機が残っていました。
子供の頃は風呂上がりに、写真だと背面にある休憩室のようなトコの自販機で「彩」っていうちょっと高級なアイスクリームを買ってもらうのが贅沢でした。コレはセンチメンタル。

ワークショップ
ワークショップ会場に戻って、フィッシュボーン図を用いたグループワークを行いました。
今回は大きなテーマ別に分かれ、「高校の活用」と「温泉の活用」のそれぞれについて、フィッシュボーン図を作成していきます。
私は「温泉の活用」の班に参加し、様々な視点から問題分析と活用のアイデアについて意見を出し合いました。

新設高校と温泉施設の活用は、全く別の問題ではなくて、その活用の手段や目的で重なるアイデアもあります。例えば、
- 温泉施設を高校の学生寮として活用する
- 合宿施設として、部の合宿や、他校を招く際の宿泊施設等に活用する
- 介護施設等として活用し、高校生がボランティアや介護体験等で関わる
- 観光客対象のビジネスを行い、高校生が商品開発したり、接客体験等で関わる
など、相互に活用されるものです。

今回のワークショップに参加して新たに気づいたこととして、以下のことがあります。
温泉の泉質が実は非常に良い(らしい)
参加者のみなさんが口々に「ありゃ湯が良ェけぇのォ…」「勿体無いよねェ…」と口々にこぼしておられました。
あまり意識したこともなかったし、最近利用していなかったのでピンとこなかったのですが、そう言われてみれば「いかにも温泉」という肌触りというか、「ヌルーン」としてそれから「サラーン」とでも言いましょうか、湯上がりには「あ〜、温泉入ったど〜」という実感と、長く続くポカポカ感があったように思います。
近くに有名な温泉街もあるので、近い泉質は期待できるのでしょうね…。
過去の経営において、アピール不足や商売下手なところがあったのでしょうか。
いずれにせよ、良い泉質の温泉を最大限活かさなければなりません。
観光客と接したい地域住民が意外と多い
今回のワークショップで同じ班になったメンバーの方の中に2人おられたんですよ。
観光客に声をかけて家に上げちゃう人
衝撃でした。割と高齢の方だったんですが、観光客を見かけると、どんな興味があって豊北町に来てくれたんだろう?って、観光客に対して興味を持っちゃうんだそうです。
それで話しかけて、楽しくて、「お茶でも飲むかね?」ってお家に招いてご馳走して、「またおいでんさい、泊めちゃるけぇ」って見送るんだそうです。
すげぇホスピタリティ。これはビジネスではできないことですよ。
今回のワークショップのまとめではこういうお宅を“プラッとハウス”とでも名付けて、例えば「こども110番の家」みたいに標識を出してもらっといて、観光客には、「“プラッとハウス”の看板が出てるお宅は休憩や交流のために訪ねてOK」ってインフォメーションを流すことを提案しました。
オッ、プラットフォームとかけて「プラッとホーム」もアリか…!?
ダサいかな?
「民泊」のもっと気軽なモンですね。観光ばっかりじゃなくて体験とか交流を目的とした旅の方には面白いだろうし、地元サイドもおしゃべり好きなお年寄りなんて、元気出るんじゃないかしら。
温泉施設の建物は建て替えが前提
老朽化の進んだ建物でしたからね…。今回せっかく視察にも行って、どんな風に活用できるか考えてみたところですが、一部だったか、本館・新館のどちらかだったか、はたまた全部だったか、取り壊して建て替えなければ使用できないそうです。耐震強度の問題とかもあるようです。
それならいっそ…って話で、今は山の上に建ってて、しかも施設までのアプローチが非常に狭く、カーブや曲がり角がキツく、大型バス向きではないってことだったので、山ごと削り取ってフラットな高さにしちゃえば良いじゃん、って意見も出てました。
ものすごい費用かかるだろうし、現在のランドマーク的な印象は薄らいじゃいますけど、アクセスは格段によくなるし、そうするとシャッター街になっちゃった商店街も、温泉街として復活する可能性が出てくるのかな…?
そういや商店街は職人街にしたらどうか?って意見が班内では出てました。陶芸とか民芸品とかの工房をズラーっと並べて、職人さんや芸術家の集う通りにしちゃう。それで体験ツアーを入れたり、お土産を生産したりする、ってお話。
ワークショップはブレインストーミング
今のところ、このワークショップは直接行政に働きかける機能はありません。
町の面白い人が集まって、ワイワイ意見を出し合ってるだけで、政策提言までは至っていない状況です。「住民の総意」とまで発展させなければそこまでの効力はない、ってコトなんでしょうね。
まちづくり協議会からどこに働きかけるべきなのか、住民からどのように支持を受けるのか、そしてそれをどうやって実現に持っていくのか…
その辺りも考えていきつつ、今はとにかくまちづくりに興味を持つ人を、(特に若い世代から)1人でも多く集めるコトかな…と思いました。