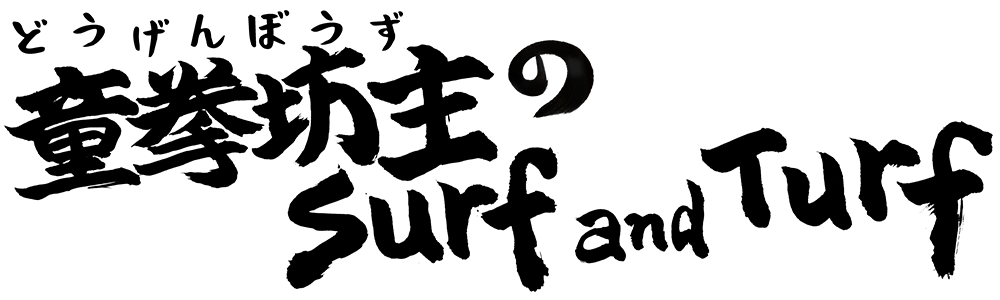田耕祭りが開催されました。外国人観光客もプラッと寄って見て行きたくなる“ザ・田舎の秋祭り”の魅力とは

INDEX
素朴な田舎の収穫祭
毎年11月3日は地区の秋祭りです。
…ですが、子供の頃は平日だった記憶があります。調べていませんが、かつては11月2日だったかも。
なにしろ、お祭りの日は学校が午後から休校になってたんです。だから11月3日 文化の日 ではなかったはず、という論理です。
最近はお祭りのお手伝いができる方も少なくなったし、お勤めの方も多いので、祝日にしたのかもしれませんね。

お祭り自体は実に素朴で、
村の鎮守の神様の 今日はめでたいお祭り日
という雰囲気。ドンドンヒャララ もありませんが。
純粋に収穫を喜び、家族や仲間の健康を祝う、そういう1日です。
ご神興
お神輿に神様を移して、祭殿に移動
お祭りの神事は、ご神興から始まります。
お神輿に神様を載せて、祭殿まで運ぶのです。
神社の建物の中で、お神輿に神様を移す神事が厳かに行われます。
私は何度か神輿を担いだことがあるのでその神事を見たことがありますが、太鼓が鳴り響く中、宮司さんが「オォオォォォォォオォォォォォ」と発し続けながら、ご神体を抱えて階段を下りてきて、お神輿に移される様子を見ると、ピリッと緊張するものです。

グリーンシートが敷かれているところで、ご神興の後の催し物が行われます。
ご神興行列の役割分担
ご神興行列は、お神輿の他にも様々な役割で構成されます。ノボリや金幣、四神鉾など、お神輿を守る道具を抱えて行列に加わる人が必要で、これらの役割は地区内の自治会が持ち回りで担当しています。

私が子供の頃は、子供の数も多く、出店がいろいろ並んで賑わっていましたが、この最近は 焼き鳥 と けいらん焼 だけです。お小遣いをもらって お菓子や、かんしゃく玉や爆竹などのおもちゃを買って境内で走り回って遊んでいたのが懐かしく思い出されます。
花を配るのが風習
お祭りの最後に、この花束から、必要なだけ花を抜き取って持ち帰る風習があります。詳細な由来は知りませんが、お守りのようなもので、家庭に1〜3本くらい飾っておきます。我が家にもあります。

花束も祭殿に持って行ってお祓いをするのでしょう。
田んぼの中の参道を祭殿場まで移動
このお祭りで最もノスタルジックな光景です。
お神輿を、田んぼを突っ切る参道の向こうの祭殿まで、行列を為して運んで行きます。

この道中で、お神輿や賽銭箱にお賽銭を投げ入れて、お神輿の下をくぐると縁起が良いとされ、何度かお神輿は立ち止まって、沿道の人に下をくぐらせてあげます。
祭殿での神事
見晴らしの良い祭殿で、神事を行います。
祝詞をあげ、巫女による「浦安の舞」が奉納されます。

巫女は、地区内の小学生くらいの女の子が選ばれ、お祭りまでに練習をします。
家族が心配そうに見守る中、巫女のふたりは 秋風に吹かれながら緊張した面持ちで舞っています。

境内で、神様と住民と 催事
祭殿から戻ってきたお神輿は境内に設置され、今度はお神輿の前で催しが行われます。グリーンシートの周りに人が集まり、楽しいことが始まる雰囲気になってきます。
私は勝手に、田舎で娯楽もなく、年に1度のお祭りで、神様も住民も一緒に、この境内で繰り広げられる催しを楽しんでいたのではないかな…、と想像しました。
何年か前には 獅子舞を披露された方がおられて、ああいうのは貴重なエンターテイメントだったのではないかな…と思います。昼寝をしている獅子に天狗がちょっかいをかけて起こして、怒って向かってくる獅子を天狗がヒラリヒラリとかわす。そしてたまに獅子が勢い余って客席に突っ込んでしまってそこにいた子供が驚き、観客から笑いが起こる…みたいな内容でした。
あたたかい雰囲気の中、催事が始まります。
浦安の舞
先ほど祭殿でも奉納された 巫女による浦安の舞です。
老人ホームからお参りに来られた利用者の皆さんが盛んに応援されていました。

住民同士の交流
このお祭りでよく見かける光景のひとつが、
「アリャ、アンタ◯◯さんトコの…」
「アッ、ハイ、長男です」
「祭りに帰ってきたかね、仕事は何しよるん? ハー、立派になってョィョ」
みたいなやりとりです。
進学や就職で地元を離れる若者が多く、こういった機会に戻ってくると、ご近所さん や スポーツ少年団でかつてお世話になった方 や、家族をよく知る人 など、例え本人が直接親しくなくても、いろいろな人に声をかけられます。これが嬉しくもあり、気恥ずかしくもあるのですが、決して悪い気はしないものです。ここが「帰ってくる場所」なんだな、と再確認できる気がします。

特にこんな風に白装束を着て神輿守をすると、急に「一丁前」感が湧いてきて、一気に交流が始まります。
鰤切り神事(デモンストレーション)
来年、2018年は浜殿祭Yearなので、直前の秋祭りとなる今回は、鰤切りのデモンストレーションを行います。先日、以下の記事で練習の様子を紹介させていただきました。
2018年4月1日の浜殿祭に向けて、鰤切りの練習が始まりました。保存版ってくらい解説します。
事前に打ち合わせをしています。今回のブリは約5kg。本番は10kg以上、昔は15kgくらいでやっていたそうですからやはり昔の方は地力がすごいです。

実際のデモンストレーションの様子はノーカット動画でどうぞ。
見学していて、来年の4月にはここを気をつけないとな…という点にいくつか気づきました。
さらに研究を深め、練習したいと思います。
餅まき
TV番組「秘密のケンミンSHOW」によると、山口県民は無類の 餅まき好き という県民性だそうですね。お祭りには 餅まき が欠かせない。確かにそうか…。週末のローカル番組で「餅まき情報」が流されてるのを観たことがあります、確かに。
このお祭りも、門から境内にお餅をまいて盛大に 餅まきが行われます。
他の 餅まき と異なるのは、餅まきが始まると宮司さんが太鼓をドンドコドンドコ叩いて盛り上げてくれること。賑やかに楽しくやったら神様もお喜びでしょう、という計らいにも見えます。

夕日に向かって 餅拾い。
なんとも良い光景でした。
終わった、と思って太鼓も止んだらそこからまさかの もうちょっとお菓子があった! ってことみたいで、ちょっとだけプレーオフもあり、皆にこやかに解散されていました。
写真は残っていませんが、先ほどの花束から、皆思い思いに花を抜き取って持ち帰っていました。
帰り道には手に餅の入ったビニール袋と数本の花を持って歩く人の列。
穏やかな天候で、良いお祭りでした。
珍しいお客さん
実は今回、神社に到着してすぐに、明らかに外国人の方だな…という雰囲気の3人組がいることに気付きました。
町内の学校や保育園にも外国人の先生が来られて外国語の授業をしてくださっているので、町内で外国人を見かけることはそう珍しくないことになってきていますが、このお祭りを見物に来る外国人は見たことがありません。
祭殿での神事を少し見学して、境内に戻った時に、アジア系の出で立ちの方に「こんにちは、どちらからお越しですか?」と日本語で声を掛けてみました。
すると「Sorry, I don’t speak Japanese.」とのことだったので、以降は英語で会話しました。
3人組は周南市で英語を教えている先生で、車で萩・角島をドライブして、たまたま帰り道に国道から神社のノボリが見えたので、何かな?と興味を持って立ち寄ったところ、エキゾチックなお祭りをやっていたので見物していたそうです。すごい偶然です。
とても素晴らしい神社だ、と感激した様子でした。
確かに、全く観光要素のない、リアルな神社ですから、外国人にはむしろ迫力があるのかもしれません。
私が海外に行っても、いかにも観光地で「おみやげ」とか日本語で書いてあるようなところより、現地の人が利用する市場であったり教会であったり、そういうところを見てみたいと思いますからね。
彼らは日本語が分からないし、日本の文化にも詳しくないでしょうから、一体何が行われているのか分からない、けどとりあえず興味深い、という様子だったので、私の拙い英語で説明してあげました。
※ 相当長いし、英語の拙さを表現するために、ルー大柴のような鬱陶しいスタイルにしてあります。時間のあるヒマな方は解読されてみてください。ただし、結論にはちょっと良い話にもってってますよ。
「アレは オミコシ というもので、そこの シュライン で プライエスト が ゴッド を ムーブ させて、そっちの フェスティバル プレイス に ブリング してるんだ」
「フェスティバル プレイス では ガールズ が トラディショナル な ダンス をしたり、ゴッド に ハーベスト を サンク したりするんだ」
「コレは 小さな ローカル フェスティバル だけど、来年は 7年に 1度の ビッグ フェスティバル がある。その時に トラディショナル な フィッシュ カッティング を披露する」
” Traditional FISH CUTTING ??? What kind of fish? ”
「イングリッシュ で何て コール するのか アイ ドント ノウ だ…」
” In Japanese? ”
「ブリ」
” Oh, Yellowtail. ”
「そうか、イエローテイル か。黄色いシッポね。」
「それで、そのビッグフェスティバルでは イエローテイル を カット する」
「1000年くらい前に、この エリア は モンゴリアン ソルジャー に アタック された」
「それで オレたちは、なんとか ウィン したんだ」
「ところが モンゴリアンソルジャー の ゴースト たちが、8年に 1度、 パワー を チャージ して、バッド シング を起こす。ディザスター や ディジーズ だ。だから オレたちは 7年に1度、そう、モンゴリアン ソルジャー の ゴースト が パワー を チャージ する前に、 オレたちの ストレングス を見せつける。 イエローテイル を モンゴリアン ソルジャー に見立てて、カット して見せるんだ」
” To scare them. ”
「イグザクトリー に ザッツ は ライト だ」
「その ビッグ フェスティバル では、オミコシ を ビーチ まで ブリングする」
” No way! By walking !? ”
「ザッツ は ライト だ。この ユーチューブ の ムービー を ウォッチ してみなよ」
(浜殿祭の行列の動画を見せる)
” Wow, amazing!! ”
「ストレングス を ショウ するために、長い長い ライン を メイク して、ビーチ までウォーク する。ところでオレは 来年の ビッグ フェスティバル では フィッシュ カッティング をやる」
” Oh, will you !? ”
「ザッツ は ライト だ。今日は ハウトゥー ドゥー イット を スタディ するんだ。ハハハ、フェスティバル を エンジョイ してくれよな」
嬉しいですね、外国人にもなんとなく、雰囲気が伝わったのでしょう。
生活に根付いたお祭りには、こういう魅力があるのか、と再認識しました。
“なんだか 良いんだよな…” って思う、ローカルな行事に対する気持ち。
ずっと当たり前に触れていると気づかないし、うまく言葉にもできませんが、なにかありますよね。そういう気持ち。
このお祭りと “お祭りマインド” は、残していきたい文化、風習です。子供たちにもこういう気持ちが芽生えて欲しい。
通りすがりの外国人旅行者に気づかせてもらいました。